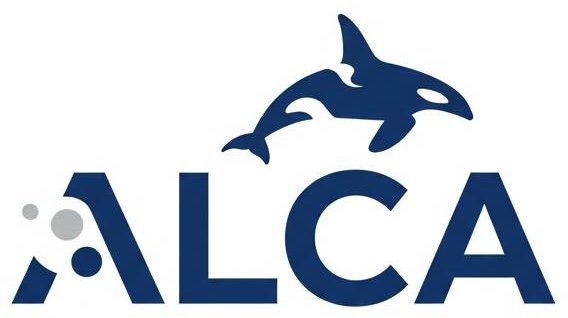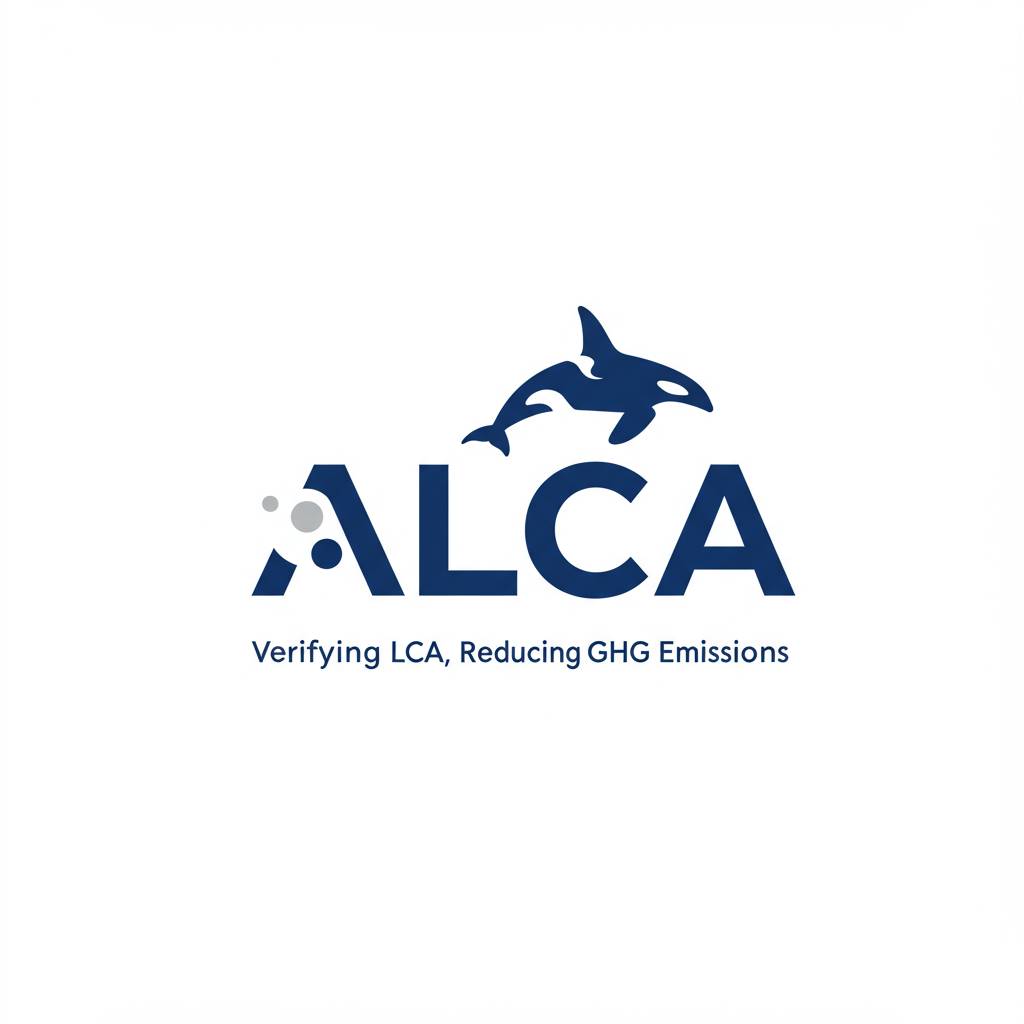はじめに
前回はGX-ETS(Green Transformation Emission Trading Scheme:排出量取引制度)への対応において、正確な排出量データを継続的に収集・算定し、報告や検証を円滑に進めるための「社内体制の整備と情報連携」の重要性について解説いたしました。部門横断的な協力体制の構築が、制度対応の鍵となることをご理解いただけたことと存じます。
今回は、いよいよ第三者検証の準備段階で企業が直面しがちな「つまずきやすいポイント」に焦点を当ててまいります。どのようなミスが起きやすく、検証機関からどのような指摘を受けやすいのか、そしてそれらを未然に防ぐための事前準備について、初心者の方や企業の担当者の皆様が実践に役立てられるよう、キーワードである「証拠書類」「記録整備」「改善勧告」を交えながら解説いたします。
検証準備で起きがちなミスと指摘されやすい点
第三者検証は、企業が報告する排出量データの信頼性を客観的に担保するための重要なプロセスです。しかし、準備不足や認識不足から、以下のようなミスや指摘を受けやすい点が散見されます。
1. 排出量データの網羅性・正確性の不足
基本的なつまずきポイントは、排出量データそのものの不備です。
| つまずきポイント | 内容 |
|---|---|
| 排出源の特定漏れ | 自社の事業活動に伴う全ての温室効果ガス排出源を特定できていないケースがあります。特に、スコープ1(直接排出)やスコープ2(間接排出)の中でも、見落としがちな小規模な排出源や、グループ会社内の特定の事業所のデータが欠落していることがあります。 |
| 活動量データの欠損・不整合 | 燃料使用量や電力消費量などの活動量データに欠損があったり、複数のデータソース間で数値が一致しなかったりする場合があります。また、計測単位の誤解や換算ミスも発生しがちです。 |
| 排出係数の不適切な適用 | 最新の排出係数を使用していなかったり、自社の実態に合わない排出係数を適用していたりするケースがあります。 |
2. 証拠書類の不備
排出量データの信頼性を裏付ける証拠書類の不備は、検証機関から最も指摘を受けやすい点の一つです。
| つまずきポイント | 内容 |
|---|---|
| 証拠書類の不足 | 算定の根拠となる請求書、領収書、メーター記録、契約書などが適切に保管されておらず、検証機関からの提示要求に応えられない場合があります。 |
| 活動量データの欠損・不整合 | 燃料使用量や電力消費量などの活動量データに欠損があったり、複数のデータソース間で数値が一致しなかったりする場合があります。また、計測単位の誤解や換算ミスも発生しがちです。 |
| 証拠書類とデータの不整合 | 報告されたデータと、それを裏付ける証拠書類の数値が一致しない、あるいは証拠書類の内容が不明瞭であるといった問題です。 |
| 保管体制の不備 | 証拠書類が散逸していたり、電子データが適切にバックアップされていなかったりすると、検証時に必要な書類を迅速に提示できません。 |
3. 記録整備の不十分さ
排出量算定のプロセスや変更履歴に関する記録整備が不十分であることも、検証時の大きな課題となります。
| つまずきポイント | 内容 |
|---|---|
| 算定プロセスの不明確さ | 誰が、いつ、どのような方法でデータを収集し、算定したのか、そのプロセスが文書化されていないと、検証機関は算定の妥当性を評価できません。 |
| 変更履歴の欠如 | 算定方法や排出源の範囲、排出係数などに変更があった場合、その理由や影響が記録されていないと、データの一貫性が疑われます。 |
| 担当者の属人化 | 特定の担当者しか算定プロセスを把握しておらず、異動や退職があった際に情報が引き継がれないリスクがあります。 |
4. 内部統制の機能不全
前回の記事でも触れた内部統制が適切に機能していない場合、データの信頼性が低下し、検証機関からの指摘に繋がります。
| つまずきポイント | 内容 |
|---|---|
| レビュー・承認プロセスの欠如 | 算定された排出量データが、複数の担当者や部署によって適切にレビュー・承認される仕組みがないと、誤りが発見されにくくなります。 |
| 責任体制の曖昧さ | 各部門の役割分担が不明確なため、データ収集や算定における責任の所在が曖昧になり、問題発生時の対応が遅れることがあります。 |
検証機関からの「改善勧告」とその対応
検証機関は、上記のミスや不備を発見した場合、その内容に応じて「改善勧告」を行います。改善勧告には、軽微なものから、排出量報告書の信頼性に重大な影響を及ぼすものまで様々です。
改善勧告への対応の重要性
改善勧告は、企業の排出量管理体制を強化し、次回の検証や制度対応をより円滑に進めるための貴重な機会です。勧告された事項に対して、企業は迅速かつ誠実に対応し、具体的な改善策を実行することが求められます。
特に、重大な不適合が指摘された場合、排出量報告書が不適格と判断され、GX-ETSにおける排出枠の取引や企業の評価に悪影響を及ぼす可能性もあります。そのため、改善勧告の内容を真摯に受け止め、再発防止策を講じることが極めて重要です。
つまずきを避けるための事前準備
これらのつまずきポイントを回避し、スムーズに検証プロセスを乗り切るためには、以下の事前準備が不可欠です。
1. 早期からの計画と準備
GX-ETSへの対応は、短期間で完了するものではありません。制度の対象となることが判明した段階で、排出量算定・報告・検証の年間スケジュールを策定し、早期から計画的に準備を進めることが重要です。
2. 担当者の育成と知識共有
排出量算定や検証に関する専門知識を持つ担当者を育成し、社内での知識共有を徹底します。定期的な研修の実施や、外部セミナーへの参加も有効です。特定の担当者に業務が集中しないよう、複数名で担当することもリスクヘッジになります。
3. 証拠書類の体系的な管理と記録整備の徹底
排出量算定の根拠となる証拠書類は、発生源ごとに体系的に整理し、いつでも参照できるように保管します。電子データの場合は、適切なバックアップ体制を構築します。また、算定プロセス、使用した排出係数、変更履歴、担当者などを詳細に文書化し、記録整備を徹底します。これにより、検証機関からの質問にもスムーズに対応できます。
4. 内部監査(自己点検)の実施
第三者検証を受ける前に、自社で排出量算定プロセスや報告書の内容について内部監査(自己点検)を実施します。これにより、事前に不備を発見し、修正する機会を得ることができます。
5. 専門家(検証機関)との事前相談
不明な点や懸念事項がある場合は、検証機関やコンサルタントなどの専門家に事前に相談することも有効です。制度解釈や算定方法に関する疑問を解消し、検証プロセスを円滑に進めるためのアドバイスを得られます。
6. 排出量管理システムの活用
排出量データの収集、算定、集計、報告、そして証拠書類の管理までを一元的に行える排出量管理システムを導入することで、手作業によるミスを減らし、効率的かつ高精度なデータ管理を実現できます。
まとめ
GX-ETSにおける第三者検証は、企業の排出量管理体制の健全性を評価する重要な機会です。証拠書類の不備、記録整備の不足、データそのものの信頼性不足といった「つまずきポイント」を理解し、早期からの計画的な準備と、適切な内部統制の構築が不可欠です。万が一、改善勧告を受けた場合でも、それを真摯に受け止め、迅速に対応することで、企業の排出量管理体制はより強固なものとなります。
次回は、GX-ETS制度の進化と今後の展望について、制度拡張や本格化の見通し、海外のETSとの比較といった視点から解説してまいります。GX-ETSへの対応でお困りの際は、経済産業省のGX-ETSにおける第三者検証機関として登録されている弊社が、皆様の制度対応を強力にサポートいたします。次回以降の解説にご期待ください。
当社は、経済産業省のGX-ETSにおける第三者検証機関として登録されており、独立した第三者検証機関としてGX-ETSにおける排出量実績報告をサポートいたします。
GX-ETS第三者検証サービスの詳細はこちらをご覧ください。
GX-ETS 第三者検証サービス
お客様が算定・報告されたGHG排出量データが、GX-ETSのガイドラインや国際基準(ISO 14064-3など)に準拠しているかを客観的に評価・確認します。
また、GX-ETSへの対応でお困りの際は、当社までお気軽にご連絡ください。
お問い合わせ参考資料
経済産業省「GXリーグ公式サイト:排出量取引制度(GX-ETS)」
https://gx-league.go.jp/action/gxets/
内閣官房GX実行会議資料「GX実行に向けた基本方針」
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/gx_jikkou_kaigi/index.html