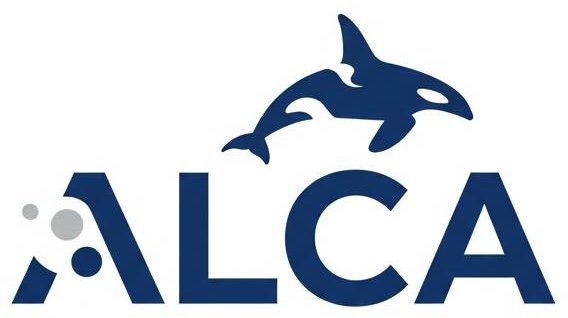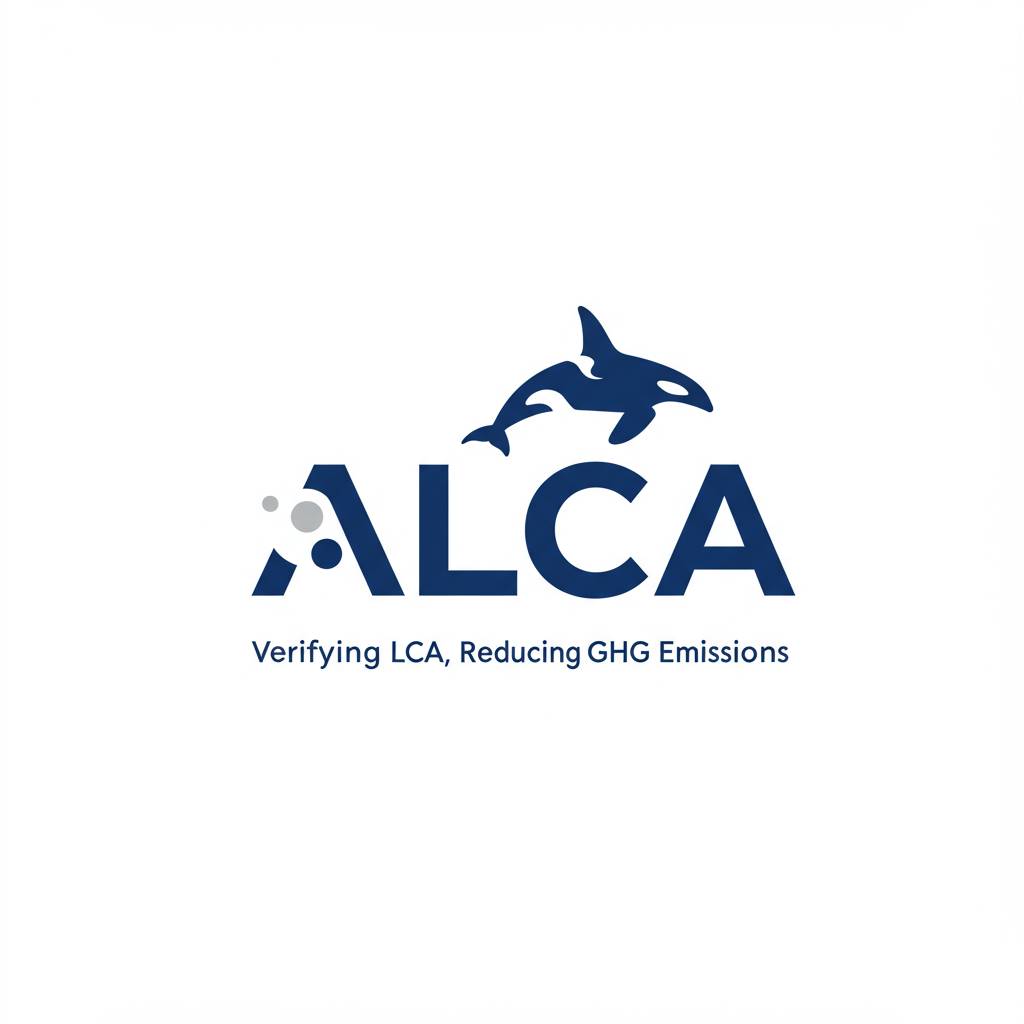はじめに
前回GX-ETSへの対応を始める企業担当者の皆様に向けて、「まずやるべきことは何か?」として、制度のタイムライン把握、排出量棚卸し、年度計画策定といった初期行動について解説いたしました。計画的な準備が、制度対応の基盤となることをご理解いただけたことと存じます。
今回は、その初期行動を進める上で避けて通れない、社内における「制度対応の社内説得術」に焦点を当ててまいります。GX-ETSへの対応は、特定の部署だけで完結するものではなく、経営層から現場の従業員まで、全社的な理解と協力が不可欠です。
どのように説明すれば、経営層のコミットメントを得られ、現場の協力を引き出せるのか、その視点と具体的な方法について、初心者の方や企業の担当者の皆様が実践に役立てられるよう解説いたします。
なぜ社内説得が重要なのか?
GX-ETSは、企業の温室効果ガス排出量に金銭的価値を付与し、排出量削減を促す制度です。これは、単なる環境規制の遵守に留まらず、企業の事業戦略、財務、組織体制、そして企業文化にまで影響を及ぼす可能性があります。
そのため、制度対応を円滑に進めるには、以下の理由から全社的な理解と協力が不可欠です。
| 社内説得の重要性 | |
|---|---|
| データ収集の広範性 | 排出量データは、生産、物流、総務、経理など、多岐にわたる部門から収集されるため、各部門の協力が必須です。 |
| 削減活動の実行 | 排出量削減は、現場での省エネ活動や設備投資など、具体的な行動を伴うため、現場の理解と実行力が求められます。 |
| 経営判断の必要性 | 排出量削減目標の設定や、排出枠の購入・売却、脱炭素技術への投資などは、経営層の戦略的な判断が必要です。 |
これらの理由から、GX-ETS対応を「自分ごと」として捉えてもらうための社内合意形成が、成功の鍵となります。
経営層への説明視点:戦略的経営課題としての提示
経営層に対しては、GX-ETSを単なるコストや規制遵守の義務としてではなく、企業の持続的な成長と競争力強化に資する「戦略的経営課題」として提示することが重要です。
1. 経営インパクトの明確化
GX-ETSが企業の経営インパクトにどう影響するかを具体的に説明します。
| コストと収益機会 | 排出枠の購入コスト、炭素賦課金といった新たなコスト要因だけでなく、排出量削減によるエネルギーコストの低減、超過削減枠の売却による収益機会、グリーンファイナンスの活用による資金調達メリットなどを提示します。 |
|---|---|
| 競争優位性 | 脱炭素化への先行投資が、将来的な市場での競争優位性や新たなビジネスチャンスに繋がる可能性を強調します。例えば、低炭素製品・サービスの開発、サプライチェーン全体の脱炭素化への貢献などが挙げられます。 |
| ブランド価値とレピュテーション | 環境への取り組みが、企業のブランドイメージ向上、顧客からの信頼獲得、優秀な人材の確保に繋がることを説明します。 |
2. リスク管理の視点からのアプローチ
GX-ETSへの対応を怠った場合のリスクを明確に示し、リスク管理の観点から制度対応の必要性を訴えます。
| 法的・経済的リスク | 制度不遵守による罰則、排出枠購入コストの増大、炭素賦課金によるコスト負担などを具体的に提示します。 |
|---|---|
| 市場リスク | 投資家からの評価低下(ESG評価の悪化)、金融機関からの資金調達困難化、サプライチェーンからの排除リスクなどを説明します。特に、海外の取引先から脱炭素化への取り組みを求められるケースが増えていることを強調します。 |
| 事業継続リスク | 気候変動による物理的リスク(異常気象、災害など)が事業継続に与える影響と、脱炭素化がそのリスク軽減に繋がることを示唆します。 |
3. 中長期的な企業価値向上への貢献
GX-ETS対応が、短期的なコストだけでなく、中長期的な企業価値向上に貢献することを説明します。例えば、脱炭素技術への投資がイノベーションを促進し、新たな市場を創造する可能性や、持続可能な経営体制の構築が企業のレジリエンスを高めることなどを伝えます。
現場への説明視点:具体的な貢献と意義の共有
現場の従業員に対しては、GX-ETS対応が自身の業務にどう関係し、どのような貢献ができるのかを具体的に説明し、モチベーションを高めることが重要です。
1. 業務への影響と具体的な協力依頼: 現場の業務にどう影響するかを具体的に説明し、協力を依頼します。
・データ収集の重要性
「皆さんが日々記録している燃料使用量や電力メーターの数値が、会社の排出量算定の基盤となります。正確なデータが、会社の脱炭素化目標達成に不可欠です」といったように、自身の業務が制度対応に直結していることを伝えます。
・省エネ活動の推進
「日々の業務における省エネ活動(電気の消し忘れ防止、設備の効率的な運用など)が、直接的に排出量削減に繋がり、会社のコスト削減にも貢献します」といったように、具体的な行動とメリットを結びつけます。
2. 意義と貢献の共有: 現場の取り組みが、会社全体、ひいては社会全体の脱炭素化に貢献することを強調し、やりがいを醸成します。
・会社の目標達成への貢献
「皆さんの協力がなければ、会社のGX-ETS目標達成は困難です。一人ひとりの行動が、会社の未来を創ります」といったメッセージを伝えます。
・社会貢献と未来への責任
「私たちの会社が脱炭素化に取り組むことは、地球温暖化対策に貢献し、持続可能な社会の実現に繋がります。未来の世代のために、今できることを共に進めましょう」といった、より大きな視点での意義を共有します。
3. 負担軽減と効率化の視点: 新たな業務負担だけでなく、効率化や改善の機会も提示します。
・業務プロセスの見直し
排出量データ収集を通じて、既存の業務プロセスにおける無駄を発見し、効率化に繋がる可能性を提示します。
・ツールの活用
排出量管理システムなどの導入により、手作業の負担が軽減され、より正確なデータ管理が可能になることを説明します。
社内合意形成のための具体的なアプローチ
経営層と現場、双方からの理解と協力を得るためには、継続的な社内合意形成の努力が不可欠です。
・定期的な情報共有と対話の場
GX-ETSに関する最新情報、自社の進捗状況、成功事例などを、社内報、イントラネット、定期的な説明会などを通じて継続的に共有します。また、質疑応答や意見交換の場を設け、疑問や懸念を解消し、現場の声を吸い上げる機会を作ります。
・成功事例の共有と表彰
他社の先進的な取り組み事例や、社内での小さな成功(例:特定の部署での省エネ達成)を共有し、具体的なイメージを持たせるとともに、貢献した部署や個人を表彰することで、モチベーション向上を図ります。
・専門家によるサポート
必要に応じて、外部の専門家(コンサルタント、検証機関など)を招き、制度説明会やワークショップを開催することも有効です。客観的な視点からの説明は、社内の理解を深める上で役立ちます。
まとめ
GX-ETSへの対応は、企業の持続可能な成長と競争力強化に直結する重要な経営課題です。経営層に対しては、経営インパクトとリスク管理の視点から戦略的な重要性を訴え、現場の従業員に対しては、具体的な貢献と意義を共有することで、社内合意形成を図ることが不可欠です。
全社的な理解と協力体制を構築することで、企業はGX-ETSへの対応を円滑に進め、脱炭素社会への貢献と企業価値向上を両立させることができるでしょう。
次回は、GX-ETS制度の理解を深めるための情報収集のすすめとして、信頼できるリソースを紹介してまいります。
当社は、経済産業省のGX-ETSにおける第三者検証機関として登録されており、独立した第三者検証機関としてGX-ETSにおける排出量実績報告をサポートいたします。
GX-ETS第三者検証サービスの詳細はこちらをご覧ください。
GX-ETS 第三者検証サービス
お客様が算定・報告されたGHG排出量データが、GX-ETSのガイドラインや国際基準(ISO 14064-3など)に準拠しているかを客観的に評価・確認します。
また、GX-ETSへの対応でお困りの際は、当社までお気軽にご連絡ください。
お問い合わせ参考資料
経済産業省「GXリーグ公式サイト:排出量取引制度(GX-ETS)」
https://gx-league.go.jp/action/gxets/
内閣官房GX実行会議資料「GX実行に向けた基本方針」
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/gx_jikkou_kaigi/index.html