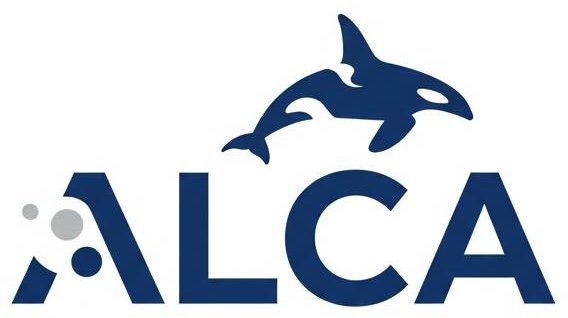はじめに
製品やサービスの環境負荷を評価し、持続可能なサプライチェーンを構築する上で、LCAデータベースの選定は極めて重要です。
特に、サプライチェーン排出量(Scope
3)の算定においては、網羅性と簡便性を両立するデータベースが求められます。
本記事では、国立環境研究所が開発・提供する「3EID(Embodied Energy and Emission Intensity Data for Japan Using Input-Output Tables)」データベースに焦点を当て、その特徴、メリット・デメリット、そして最適な活用方法について詳細に解説します。
1. なぜ今、3EIDがLCA担当者から注目されているのか
近年、企業にはサプライチェーン全体の温室効果ガス(GHG)排出量算定と情報開示が強く求められています。
特にScope3排出量は、その範囲の広さからデータ収集が困難なケースが多く、網羅的かつ効率的な算定を可能にするデータベースへのニーズが高まっています。
3EIDは、日本の産業構造を詳細に反映した産業連関表を基に、財・サービス生産に伴う環境負荷原単位を提供するデータベースです。
その特徴は、日本の経済活動全体を網羅的にカバーできる点、そして無料で利用可能である点にあります。
2. 3EIDの概要と開発経緯
3EIDは、国立研究開発法人
国立環境研究所が開発・提供する「産業連関表による環境負荷原単位データベース」です。
その名称は「EmbodiedEnergy andEmissionIntensityData for Japan
Using Input-Output
Tables」の頭文字から取られており、エネルギー(Energy)、環境(Environment)、経済(Economy)の「3E」問題を解決するための指標(Indicator)の一つとして活用されることを目指しています。
開発は1997年にCO2を対象とした環境負荷原単位の収録から始まり、2002年にはエネルギー消費量と大気汚染物質を環境負荷項目に加えた「3EID」として整備が開始されました。日本の総務省が作成する「産業連関表」の新規発行に合わせて、最新のデータに更新が続けられています。
産業連関表は、生産活動の種類によって区分された約400の部門で構成され、各部門間の経済的なつながりを年間の取引額で表した行列形式の統計表です。
3EIDの環境負荷原単位は、この産業連関表を基に産業連関分析によって算出されており、各部門の単位生産活動(例えば100万円相当の生産)に伴って直接的・間接的に発生する環境負荷量を示します。
3EIDは、環境システム研究の基盤データとして利用されるだけでなく、企業のサプライチェーンを通じたGHG排出量や製品のカーボンフットプリントの推計にも活用されています。
また、データの透明性を重視し、推計方法の詳細な解説や、算定の根拠となる各種データ(部門別の燃料消費量、排出係数など)も公開されており、利用者が算定過程を把握しやすいように工夫されています。
3. 最大の特徴:メリットとデメリット
3EIDは産業連関法を用いたデータベースとして、特定の強みと利用上の注意点を持っています。
メリット(強み)
| 高い網羅性と簡便性 | 日本の産業連関表を基にしているため、日本国内のほぼ全ての経済活動を網羅的にカバーしています。これにより、特定の製品やサービスのサプライチェーン全体を詳細に追跡する手間をかけずに、広範囲の環境負荷を概算できます。特にScope 3排出量算定において、データ収集が困難なカテゴリやサプライヤーからの一次データが得られない場合に、非常に有効なツールとなります。 |
|---|---|
| 無料での利用可能 | 国立環境研究所が提供しているため、基本的に無料で利用できます。これにより、LCA導入の初期コストを抑えたい企業や、LCAの試行的な算定を行いたい企業にとって大きなメリットとなります。 |
| 間接的な環境負荷の把握 | 産業連関分析の特性上、特定の製品やサービスの生産活動に伴う直接的な排出だけでなく、その生産に必要な原材料やエネルギーの調達、さらにはそれらの生産に必要な全てのサプライチェーン上の間接的な環境負荷まで含めて評価できるため、包括的な排出量を把握できます。 |
| 透明性の高さ | 推計方法や基礎データが公開されており、データの信頼性を確認しやすい点が挙げられます。これにより、算定結果の根拠を明確にし、社内外への説明責任を果たす上で役立ちます。 |
デメリット(利用上の注意点)
| 部門の粗さ(平均値の限界) | 産業連関表は約400の部門に分類されていますが、これは個々の製品やサービスを詳細に区別するには粗い場合があります。一つの部門に含まれる複数の製品の平均的な環境負荷原単位となるため、特定の製品のLCAを詳細に評価する際には、実態との乖離が生じる可能性があります。例えば、「自動車製造」部門の原単位は、電気自動車とガソリン車を区別しない平均値となるため、個別の製品の環境性能差を正確に反映することは困難です。 |
|---|---|
| 金額ベースによる価格の歪み | 産業連関表は基本的に金額ベースの取引データを使用しています。このため、物価変動や為替レートの影響、あるいは製品の付加価値の高さが環境負荷とは直接関係なく原単位に影響を与える可能性があります。高価な製品ほど環境負荷が高いと誤解される、あるいはその逆のケースが生じることも考えられます。 |
| データの古さ | 産業連関表は数年ごとに作成されるため、最新の産業構造や技術革新がリアルタイムで反映されていない場合があります。特に技術進歩の速い分野では、データの鮮度が課題となることがあります。 |
| プロセスデータの欠如 | プロセス法データベースのように、個々の製造プロセスの詳細な入出力データは含まれていません。そのため、特定のプロセスにおける改善余地を特定したり、自社固有のデータ(一次データ)を詳細に組み込んだハイブリッドLCAを実施したりする際には、別途プロセス法データベースや自社データの活用が必要となります。 |
| 特定の環境影響項目への対応 | 主にエネルギー消費量と温室効果ガス排出量に焦点を当てていますが、水資源や土地利用など、他の環境影響領域に関するデータは限定的である場合があります。 |
4. 課題点と今後の展望
3EIDは日本のLCA実務において大きな貢献をしてきましたが、さらなる活用に向けていくつかの課題と今後の展望が考えられます。
課題点
・細分化されたニーズへの対応
産業構造の変化や、より詳細な製品レベルでのLCA算定ニーズの高まりに対し、現行の約400部門という分類では限界があります。特定の製品カテゴリや新技術に対するより詳細な原単位の提供が求められています。
・データの鮮度と更新頻度
産業連関表の作成頻度に依存するため、データの更新が数年ごととなる点が、急速に変化する産業界の現状をタイムリーに反映する上での課題です。
・プロセス法データとの連携強化
産業連関法の強みである網羅性と、プロセス法の強みである詳細性を組み合わせるハイブリッドLCAの重要性が増しています。3EIDが他のプロセス法データベースとの連携をよりスムーズに行えるような仕組みやガイダンスの充実が期待されます。
今後の展望
・データ品質の向上と透明性の維持
環境負荷原単位の推計方法のさらなる精緻化や、データソースの明確化により、信頼性の向上を図ることが期待されます。
国際的な互換性の向上
国際的なLCAの動向や標準化の動きに対応し、海外のデータベースやツールとの連携を容易にすることで、グローバルなサプライチェーン評価における利便性を高める可能性があります。
利用シーンの拡大に向けた情報提供
3EIDの利用方法に関する詳細なチュートリアルや、具体的な活用事例の提供を通じて、LCA担当者がより効果的にデータベースを使いこなせるよう支援することが期待されます。
5. 想定される利用者と活用シーン
3EIDは、その特性から以下のような利用者や活用シーンに最適です。
・LCA算定の初期段階にある企業
LCAの導入を検討している企業や、サプライチェーン排出量算定をこれから始める企業にとって、無料で広範囲のデータを利用できる3EIDは、手軽に全体像を把握するための有力な選択肢となります。
・サプライチェーン全体のホットスポット分析を行いたい企業
Scope3排出量の算定において、どのカテゴリやサプライヤーが環境負荷の大きな要因となっているかを大まかに把握し、削減に向けた優先順位を付ける際に有効です。
・学術研究機関や公共機関
環境政策の立案、産業構造分析、環境効率評価など、マクロな視点での環境研究に活用されます。
・一次データ収集が困難な企業
サプライヤーからのデータ提供が得られない場合や、非常に複雑なサプライチェーンを持つ企業が、網羅的な排出量を概算する際に補助的に利用できます。
・国内の製品・サービスの概算評価
特定の製品やサービスの詳細なLCAではなく、日本国内における平均的な環境負荷を概算したい場合に適しています。
例えば、自社製品の原材料調達におけるGHG排出量を簡易的に把握したい製造業や、自社の事業活動全体におけるScope 3排出量の概算値を算出したいサービス業などが、3EIDの主な利用者となるでしょう。
まとめ
3EIDデータベースは、国立環境研究所が提供する日本国内の産業構造に特化した環境負荷原単位データベースであり、特にサプライチェーン全体の環境負荷を網羅的かつ効率的に概算したい企業にとって非常に有用なツールです。
無料であること、そして日本の経済活動を詳細に反映している点は大きなメリットですが、部門の粗さや金額ベースの特性、データの鮮度といったデメリットも理解した上で活用することが重要です。
LCAの目的や要求精度に応じて、3EIDを他のプロセス法データベースや自社データと組み合わせることで、より精緻なLCA算定が可能になります。
3EIDは、LCAの第一歩を踏み出す企業や、サプライチェーン全体の環境パフォーマンスを俯瞰的に把握したい企業にとって、強力な味方となるでしょう。
3EIDをはじめとするLCAデータベースの選定や、それを活用したLCA算定を実施する場合、LCAを専門とするコンサルタントに依頼・相談することも可能です。
ALCAでは、LCAの専門家がお客様の目的や状況に合わせて、LCAやCFPの算定を適切にサポートいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ参考資料
国立研究開発法人国立環境研究所「3EID -
産業連関表による環境負荷原単位データベース」
https://3eid.nies.go.jp