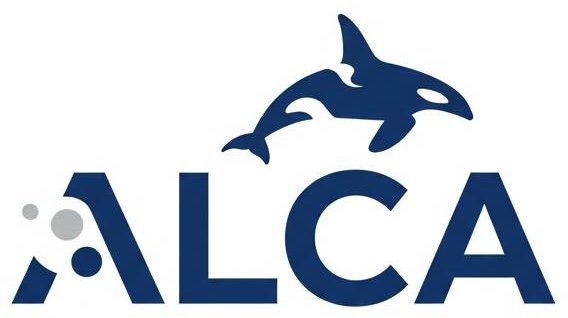はじめに
前回の記事では、建築物のライフサイクル全体でCO2排出量を評価するLCCO2の算定アプローチや、J-CATのような具体的なツールについて解説しました。
本記事では、このLCCO2の算定・評価・削減を推進することが、環境負荷の低減に貢献するだけでなく、企業や建築物オーナーにどのようなビジネス上のメリットをもたらすのかを詳しく見ていきます。
環境面での効果
LCCO2の算定と評価を推進することで、建築物のライフサイクル全体におけるCO2排出量を定量的に把握し、削減目標設定や効果的な対策の立案が可能となります。これにより、以下のような環境面での効果が期待できます。
| 環境面での効果例 | |
|---|---|
| CO2排出量の削減 |
各ライフサイクル段階での排出量を「見える化」することで、排出量の多い段階や削減ポテンシャルの高い部分を特定し、具体的な削減策(高効率設備の導入、再生可能エネルギーの活用、低炭素建材の利用など)を講じることができます。
これは、日本の2050年カーボンニュートラル目標達成に向けたCO2排出量削減に直接貢献します。 |
| 資源・エネルギー消費の最適化 | LCCO2評価は、広義のLCAの一部であり、エネルギー消費やコストと組み合わせて評価されることもあります。これにより、CO2だけでなく、資源やエネルギーの消費量も考慮した環境負荷の低減策を検討できます。 |
| 長寿命化の促進 | 建築物の耐久性向上や将来の改修に対応しやすい設計は、建て替え周期を長くし、新築時や解体時のCO2排出量を削減する効果があります。ライフサイクル全体でCO2排出量をマイナスにするLCCM住宅のような取り組みも普及が進んでいます。 |
算定・評価手法と技術的アプローチ
建築物のLCCO2を算定・評価するためには、専門的な手法やツールが開発されています。
| 手法・ツール名称 | |
|---|---|
| 建物のLCA指針 |
日本建築学会が中心となり、建築物のLCA評価手法やデータベースを整備しています。
この指針に基づいた計算ツールも提供されており、構造種別、面積、建て替え周期、資材量、運用エネルギー消費量などを入力してLCCO2を算出できます。 |
| CASBEE(建築環境総合性能評価システム) | 2001年に開発された建築物の環境性能を総合的に評価するツールです。LCCO2評価はCASBEEの評価項目に組み込まれており、既存建築物の評価や改修計画においても活用されています。 |
| その他の評価システム・ツール | 国土交通省によるグリーン庁舎評価システム(GBES)や、東京都財務局による都有施設環境・コスト評価システムなど、特定の建築物用途や主体に特化した評価システムも開発されています。これらのシステムは、建材のCO2排出原単位やエネルギーのCO2排出係数といったデータベースを用いてLCCO2を算出します。 |
| 企業独自の開発ツール | 近年では、建設会社などが独自のLCCO2評価ツールを開発し、設計の早期段階でのシミュレーションに活用しています。例えば、大林組は2024年11月に「カーボンデザイナー E-CO BUILDER」を開発しました。このツールは、建設時と運用時のCO2排出量削減効果、建設コスト、運用コストなどを瞬時に比較検証できます。 |
実施例とケーススタディ
LCCO2算定・評価は、既に具体的なプロジェクトで活用されています。
| 実施例 | 概要 |
|---|---|
| 政府庁舎の評価事例(GBES) | 国土交通省のグリーン庁舎評価システムを用いた試算では、省エネ設備などを導入することで、LCCO2排出量(運用時)が約7%〜15%削減される結果が得られています。 |
| 東京都の都有施設評価事例 | 東京都財務局のシステムを用いた庁舎モデルの評価では、環境配慮手法を導入することで、運用CO2排出量が15%~44%、LCCO2が8%~20%低減される結果が得られています。 |
| LCCM住宅の普及 | 国土交通省は、高断熱・高気密、高効率設備に加え、太陽光発電などでライフサイクル全体のCO2排出量をマイナスにするLCCM住宅の普及を促進しており、支援事業も実施しています。 |
企業におけるメリット
LCCO2の推進は、環境負荷低減という社会的貢献に加え、企業や建築物オーナーに多くのビジネス上のメリットをもたらします。
| メリット例 | 概要 |
|---|---|
| 企業価値・ブランドイメージの向上 | 環境問題への積極的な取り組みは、企業の社会的責任(CSR)として評価され、ステークホルダー(投資家、顧客、地域社会)からの信頼獲得や企業価値の向上につながります。 |
| 競争力の強化 |
環境性能の高い建築物は、テナント誘致や不動産価値向上において有利に働きます。特にLCCO2などの明確な評価基準に基づく環境性能は、競合との差別化要因となります。
建設業界では、入札や工事成績評定でCO2排出量削減が評価され、加点につながる動きも見られます。 |
| コスト削減 | 運用段階での省エネルギー化は、光熱費の削減に直結します。また、長寿命化や適切な維持管理計画により、ライフサイクル全体での修繕・改修コスト(LCC)を抑制できる可能性があります。 |
| 新しい技術・サービスの開発促進 | LCCO2削減目標の達成は、革新的な建材、高効率設備、再生可能エネルギー技術などの研究開発を促進します。これにより、新たなビジネス機会創出や技術的優位性の確立につながります。 |
| リスク管理 | 将来的な炭素税導入や環境規制強化のリスクを低減できます。LCCO2評価を通じて早期に対策を講じることで、将来の追加コストや事業継続リスクを回避できます。 |
| 従業員の意識改革 | 環境問題への取り組みは、従業員の環境意識を高め、業務プロセスや職場環境の見直しを促し、結果として業務効率化や生産性向上につながる可能性もあります。 |
課題と今後の展望
LCCO2の推進には、専門知識の必要性、計画的な環境整備、業務内容の大幅な見直しが必要となる場合があるといった課題も存在します。特に中小規模の事業者にとっては、これらのハードルが高い可能性があります。
一方で、カーボンニュートラル社会の実現に向け、建築分野におけるLCCO2の重要性は今後さらに高まります。
今後は、評価ツールの使い勝手改善や評価負担軽減、LCAコンサルティングへの外注・委託などを通して、少しづつ進めていくことが重要です。
LCAコンサルティングへの外注・委託についてはこちら:LCA外注・委託の費用相場と依頼先の選び方
まとめ
建築物のライフサイクル全体でCO2排出量を評価するLCCO2は、2050年カーボンニュートラル実現に向けた建築分野の重要な取り組みです。
LCCO2の推進は、CO2排出量削減、資源・エネルギー最適化、廃棄物削減、長寿命化といった環境効果に加え、企業価値向上、競争力強化、コスト削減、技術開発促進、リスク管理、従業員意識改革といった多岐にわたるビジネスメリットをもたらします。
日本政府も制度導入やツール開発、支援事業を通じてLCCO2の普及を後押ししており、建築業界にとってLCCO2への対応は、持続可能な成長と新たなビジネス機会創出に不可欠な要素となっていきます。
様々な制度や補助をうまく活用しつつ、自社の脱炭素化や規制対応を進めていくことが重要です。次回の記事では、その中でも政府補助金についてご紹介します。
参考文献
国土交通省、建築物のライフサイクルカーボンの算定・評価等を促進する制度に関する検討会
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk4_000302.html
一般社団法人静岡県環境資源協会、令和6年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業Q&A
集
https://siz-kankyou.com/wp-content/uploads/2024/09/r6-zebco2-lczebqa2.pdf
株式会社大林組、建物計画の初期段階でCO2排出量削減効果とコストを比較検証できる「カーボンデザイナー
E-CO BUILDER™」を開発
https://www.obayashi.co.jp/news/detail/news20241114_1.html