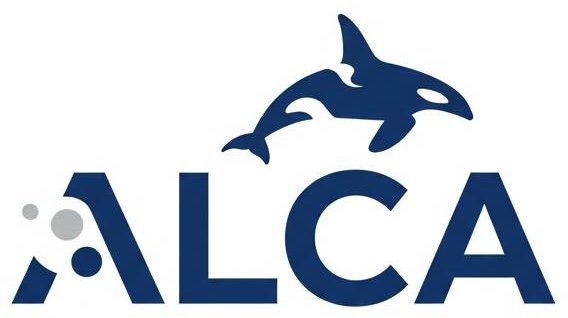はじめに
前回の記事では、建築物のライフサイクル全体でCO2排出量を評価するLCCO2の重要性や、その算定・評価アプローチについて解説しました。
本記事では、このLCCO2削減を加速させるために、日本政府や関連機関がどのような支援制度を構築し、推進しているのかを、初心者や企業担当者にも分かりやすくご紹介します。
概要:LCCO2削減を後押しする国の支援
脱炭素社会の実現に向けた国際的な要請と国内目標の高まりを受け、建築分野における温室効果ガス排出量削減の重要性が増しています。特に、建物の運用段階だけでなく、資材製造から建設、維持管理、解体・廃棄に至るライフサイクル全体(LCCO2)での排出削減が不可欠です。
日本政府は、この課題に対応するため、環境省、国土交通省、経済産業省、農林水産省といった関連機関が連携し、多様な支援制度を構築・推進しています。これらの制度は、ZEB(Net Zero Energy Building)化や省CO2化を軸に、建築物のLCCO2削減を加速させることを目的としています。
2024年度には、これまでの実証的な取り組みから、制度の普及促進へとシフトし、より実践的な脱炭素化の取り組みを後押しする体制が強化されています。
これらの支援事業は、企業の費用負担を軽減しつつ、革新的な技術導入やLCCO2削減に向けた具体的な行動を促進することで、2050年カーボンニュートラル目標および2030年度の温室効果ガス46%削減目標(2013年度比)の達成に貢献することを目指しています。
主要な支援事業とその連携
建築物のLCCO2削減を促進するための中心的な支援事業として、環境省が主導し、関係省庁と連携して実施される「建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業」があります。
この事業は、業務用施設のZEB化や省CO2化の普及に資する高効率設備等の導入を支援するもので、2024年度からは以下の7種類の支援パターンが用意されています。
| 支援事業 | 所管省庁 | 概要 |
|---|---|---|
| LCCO2削減型の先導的な新築ZEB支援事業 | 環境省、国土交通省連携 | 建築物の運用時だけでなく、ライフサイクル全体でのLCCO2削減を目指す先導的な新築ZEBを支援します。LCCO2の算出・削減、再生可能エネルギーの導入などが要件となります。 |
| ZEB普及促進に向けた省エネルギー建築物支援事業 | 環境省、経済産業省連携 | 長期間使用される建築群や単体建築物のZEB化普及を支援します。新築・既存建築物の両方が対象で、ZEB化に資する高効率設備等の導入を支援します。 |
| 国立公園利用施設の脱炭素化推進事業 | 環境省 | サステナブルな観光地「ゼロカーボンパーク」内の国立公園利用施設の脱炭素化を支援します。 |
| 水インフラにおける脱炭素化推進事業 | 環境省、国土交通省、経済産業省連携 | 上下水道施設やダム施設における脱炭素化を目的とし、再生可能エネルギー設備や高効率設備等の導入を支援します。 |
| サステナブル倉庫モデル促進事業 | 環境省、国土交通省連携 | 物流施設において、省CO2化・省人化機器と再生可能エネルギー設備の同時導入を支援し、サステナブル倉庫モデルの普及を目指します。 |
| 省CO2化と災害・熱中症対策を同時実現する施設改修等支援事業 | 環境省、国土交通省連携 | 業務用施設の改修において、熱中症対策にも資する高効率機器等の導入を支援し、既存建築物のCO2排出量削減を目指します。 |
| CE×CNの同時達成に向けた木材再利用の方策等検証事業 | 環境省、国土交通省連携 | 建築分野における資源の循環利用(サーキュラーエコノミー:CE)と脱炭素(カーボンニュートラル:CN)の同時達成に向け、木材再利用の方策検証や普及促進を支援します。 |
これらの事業は、各省庁の専門性や管轄分野を活かしつつ連携することで、建築物の用途やライフサイクルの各段階に応じた包括的な支援を提供しています。特に、LCCO2削減型の事業では、国土交通省との連携により、建築時の排出削減にも焦点を当てています。
技術的アプローチと推進される要素
政府の支援事業では、LCCO2削減を実現するための様々な技術的アプローチや要素の導入が推進されています。主要なものとして、以下の点が挙げられます。
| 技術的アプローチ | 概要 |
|---|---|
| 高効率設備・システムの導入 | 空調、換気、給湯、照明などのエネルギー消費が大きい設備を高効率な機器に更新することで、運用段階のCO2排出量を大幅に削減します。 |
| 再生可能エネルギーの導入 | 太陽光発電設備など、建築物やその周辺で再生可能エネルギーを導入・活用することで、運用段階のエネルギー消費に伴うCO2排出を実質ゼロに近づけます。 |
| エネルギー管理体制(BEMS等) | エネルギー消費量を計測・可視化し、データに基づいた分析・評価や設備の通信・制御を行うエネルギー管理システム(BEMS等)の整備が多くの事業で要件とされており、継続的な省エネルギー運用を可能にします。 |
| 外皮性能の向上 | 断熱材や高性能窓の導入による外皮(壁、屋根、窓など)の断熱性・気密性の向上は、空調負荷を低減し、省エネルギー効果を高める基本的なアプローチです。 |
| 木材・CLTの利用促進 | 建築物への木材利用は、炭素固定効果に加え、製造時のCO2排出量が他の建材と比較して少ないことから、LCCO2削減に貢献します。 |
| フロン類排出抑制対策 | 冷媒等に使用されるHFCsは温室効果が非常に高いため、機器使用時の漏洩監視や廃棄時の適切な回収が重要視されています。 |
| ライフサイクルアセスメント(LCA) | 建築物のライフサイクル全体でのCO2排出量を算定・評価するLCAの実施が、LCCO2削減型事業の要件となっています。環境省は日本の建築事情に合わせた算定ツールJ-CATを2024年10月に公開し、普及を促進しています。 |
| BIMとの連携(GX/DX) | 建築分野のデジタルトランスフォーメーション(DX)としてBIM(Building Information Modeling)の普及が推進されており、LCCO2削減(GX)と連携した取り組みが進められています。 |
制度的枠組みと関連施策
政府の建築分野における脱炭素化推進は、個別の支援事業だけでなく、より広範な制度的枠組みや関連施策によって支えられています。
政府実行計画
政府自身の事務・事業における温室効果ガス排出削減計画であり、野心的な目標を掲げています。建築物の省エネルギー徹底に加え、LCCO2削減が位置付けられています。
環境配慮契約法
国や独立行政法人等の建築物に係る契約において、ライフサイクルを通じた脱炭素化を図るため、エネルギー消費量データに基づく対策評価や技術提案を求めるプロポーザル方式の採用などが求められています。
不動産分野における気候関連情報開示
ESG投資の拡大を背景に、不動産分野でも企業のScope3排出量(LCCO2を含む)の情報開示が金融市場から求められています。
サプライチェーン排出削減の促進
中小企業を含むバリューチェーン全体での脱炭素化を進めるため、取引先への働きかけ(サプライヤーエンゲージメント)を支援するモデル事業や、業界単位でのScope3算定ルール共通化の取り組みが進められています。
具体的な成果と事例
「LCCO2削減型の先導的な新築ZEB支援事業」の2024年度一次公募では、8件の事業が採択されました。これらの事業では全てJ-CATを用いてLCCO2算定が行われ、平均的なLCCO2排出量の内訳は、運用段階の排出量が大きいものの、資材製造や維持管理段階の排出も無視できない割合を占めていることを示しており、LCCO2削減の重要性を裏付けています。
公共建築物の分野では、政府実行計画に基づき脱炭素化が進められています。例えば、名古屋第4地方合同庁舎は、設計段階でZEB Ready基準を達成しており、公共部門が率先してZEB化とLCCO2削減に取り組む具体的な事例となります。
課題と今後の展望
建築分野におけるLCCO2削減に向けた政府・関連機関の支援は、2024年度に普及促進段階へ移行し、多様な事業を通じて取り組みが加速しています。
しかし、いくつかの課題も存在します。多くの支援事業で補助率や上限額が未定である点は、事業計画を立てる上での不確実性となり得ます。また、LCCO2算定やデータ管理、新たな技術の導入には一定の専門知識やコストが必要であり、特に中小事業者にとってはハードルとなる可能性があります。
今後の展望としては、支援制度の具体的な要件や補助内容の明確化が進むとともに、J-CATのような算定ツールの普及や、BIMとの連携による効率的なLCCO2評価手法の確立が期待されます。また、サプライチェーン全体での排出削減に向けた取り組みや、環境性能の高い建築物・建材が市場で正当に評価される仕組みづくりも重要となるでしょう。
まとめ
建築物のライフサイクル全体でCO2排出量を評価するLCCO2は、2050年カーボンニュートラル実現に向けた建築分野の重要な取り組みです。日本政府は、環境省、国土交通省、経済産業省、農林水産省といった関連機関が連携し、「建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業」をはじめとする多様な支援制度を構築・推進しています。
これらの制度は、LCCO2の可視化と削減を促し、企業のコスト負担を軽減しつつ、革新的な技術導入や具体的な行動を促進することを目的としています。
LCCO2の推進は、CO2排出量削減、資源・エネルギー最適化、廃棄物削減、長寿命化といった環境効果に加え、企業価値向上、競争優位性強化、コスト削減、技術開発促進、リスク管理、従業員意識改革といった多岐にわたるビジネスメリットをもたらします。建築業界にとってLCCO2への対応は、持続可能な成長と新たなビジネス機会創出に不可欠な要素となっています。
建築物のLCCO2算定や第三者検証にご興味をお持ちの方は、ぜひ弊社のLCA算定支援サービスをご検討ください。専門家が貴社の脱炭素戦略をサポートいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ