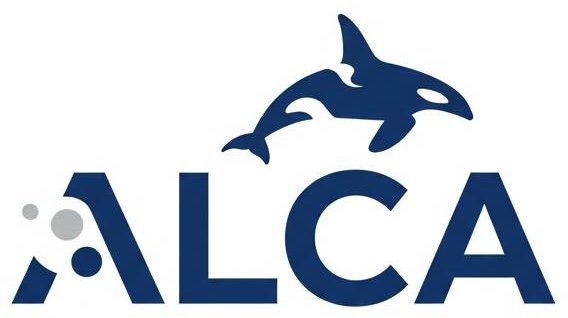はじめに
CBAM(Carbon Border Adjustment Mechanism)は、EUが導入する炭素国境調整メカニズムで、2023年10月から移行期が始まり、2026年に本格運用されます。
EU域外から輸入する特定のカーボン集約製品に対し、輸出国における製造段階のGHG排出に「炭素価格」を課す制度です。
CBAMの目的
CBAMの導入には、主に以下の目的があります。
・カーボンリーケージ(炭素漏れ)防止:EU国内の産業がコストの安い未規制国に移転するのを防ぎ、気候効果を持続する
・EU ETSとの整合性:EU排出量取引制度(ETS)と連動し、輸入品も同等の炭素費用を負担する構造
・国際的な炭素価格の普及促進:輸出元国にも炭素規制導入を促す効果が期待されます
運用スケジュール
| フェーズ | 内容 |
|---|---|
| 2023年10月〜2025年末(移行期間) | 鉄鋼・アルミ・セメント・肥料・電力・水素など6品目に対して、排出量報告が四半期ごとに義務化(炭素コストは未発生) |
| 2026年以降(本格導入) | 輸入業者はETS価格連動のCBAM証書を購入・納付する義務が開始 |
| 2030年以降 | EU ETS対象全商品に拡大予定 |
企業に求められる対応
・対象製品の確認
CBAM対象6品目に該当するかをチェック(川下製品拡大の可能性あり)
・体化排出量の定量化
直接排出(Scope 1)+間接排出(Scope
2)を両方合算し、排出量を算定。
測定等級:自社測定値やデフォルト値(平均値)利用可能だが、報告・検証には実測が望ましい。
・報告体制の整備
移行期は四半期報告、本格導入期は年次申告書提出。
認可輸入業者による登録制度や、EU指定のCBAM登録簿への申告が必要。
・第三者検証の取得
実測ベースで排出量報告した場合、認定検証者による検証報告書の取得が義務化。
・CBAM証書の購入と納付
ETS価格に連動する証書を購入し、その費用を炭素コストとして輸入時に納付。既に排出権を支払った場合は相殺可能。
CBAMの制度影響とメリット
CBAMの導入は、企業にとって新たなビジネスチャンスと同時に、対応すべき課題ももたらします。
・透明性強化
EU基準に従った排出量算定を通じてサプライチェーン全体の透明性が向上。
・競争力維持
炭素コスト転嫁の負担を逐次把握することで、価格競争で不利にならず済みます。
・制度適応の先行者メリット
早期準備により、コスト・体制構築での優位性が得られます。
まとめと提言
CBAMは単なる規制ではなく、EU市場で事業を継続する上で不可欠な環境コスト管理ツールです。担当者にとっては、「製品の排出量」を精度高く把握し、算定→報告→検証→証書納付という一連のフローを整える実務の転換点となります。
参考資料
独立行政法人日本貿易振興機構、EU炭素国境調整メカニズム(CBAM)の解説(基礎編)(2024年2月)
https://www.jetro.go.jp/world/reports/2024/01/b56f3df1fcebeecd.html
経済産業省、欧州炭素国境調整措置
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/factory/procedure/