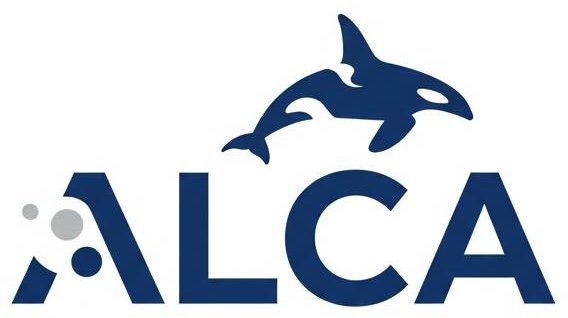はじめに
2050年カーボンニュートラルと経済成長の両立を目指す日本において、その実現の根幹をなすのが「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律」(通称:GX推進法)です。
2023年5月に公布され、2024年4月1日に施行されたこの法律は、従来の環境規制とは一線を画し、脱炭素化を新たな成長の機会と捉え、官民一体での大規模な投資を促すことを目的としています。
本記事では、企業の気候変動担当者向けに、GX推進法の概要、その全体像、そして企業に課される具体的な義務について解説します。
GX推進法とは:法律の概要と目的
GX推進法は、日本が2050年カーボンニュートラルという国際公約を達成しつつ、同時に産業競争力を強化し、経済成長を実現するための法的基盤です。
この法律は、化石燃料に依存した社会・産業構造から、クリーンエネルギーを基盤とした構造への転換(グリーントランスフォーメーション:GX)を円滑に進めることを目指しています。
従来の環境法が排出規制や罰則に重点を置いていたのに対し、GX推進法は「投資」と「成長」をキーワードに、脱炭素化に向けた民間企業の先行投資を強力に後押しする点が最大の特徴です。
今後10年間で官民合わせて150兆円を超えるGX投資を呼び込むことを目標としています。
GX推進法の全体像:3つの柱とGX推進機構
GX推進法は、その目的達成のために、主に以下の3つの柱と、それを実行する「GX推進機構」によって構成されています。
1. GX投資の促進
脱炭素化に向けた大規模な投資を促すため、政府は「GX経済移行債」を発行します。これは、2023年度から10年間で約20兆円規模の国債であり、その資金は再生可能エネルギーの導入、水素・アンモニア発電技術の開発、次世代原子力技術開発、蓄電池やカーボンリサイクル燃料などの革新技術開発、設備投資、需要創出といった脱炭素化に資する幅広い分野への支援に充てられます。
この投資促進策は、単なる補助金ではなく、企業の脱炭素投資を収益に結びつけるための税制優遇や金融支援と組み合わされることで、民間投資を呼び込む仕組みとなっています。
2. 成長志向型カーボンプライシングの導入
CO2排出に価格を付けることで、GX関連製品や事業の収益性を高め、脱炭素投資を促進する仕組みです。これは以下の2つの要素で段階的に導入されます。
・エネルギー使用の合理化に関する基本方針の策定化石燃料賦課金
2028年度以降、化石燃料の輸入事業者などから、輸入する化石燃料に由来するCO2量に応じて徴収されます。当初は低い負担額から開始し、徐々に引き上げられる方針です。
・特定事業者負担金(排出量取引制度)
2033年度以降、発電事業者に対し、CO2排出枠の一部を有償で割り当て、その量に応じた負担金が徴収されます。事業者間で排出枠を売買できる市場が整備され、排出枠の価格は入札方式で決定されます。
これらのカーボンプライシングによる収入は、GX経済移行債の償還財源として活用され、脱炭素投資の好循環を生み出すことを目指します。
3. GX推進戦略の策定・実行と進捗評価
政府は、GXを総合的かつ計画的に推進するための「脱炭素成長型経済構造移行推進戦略」を策定し、実行します。
この戦略は、エネルギー安定供給の確保を大前提とし、徹底した省エネルギーの推進、再生可能エネルギーの最大限の導入、安全性を確保した上での原子力発電の活用などを盛り込みます。
また、GXへの取り組みの進捗状況や国内外の経済動向を踏まえ、施策のあり方について定期的に評価・見直しが行われます。
GX推進機構の設立
これらの施策を円滑に推進するため、経済産業大臣の認可により「GX推進機構」(脱炭素成長型経済構造移行推進機構)が設立されます。
この機構は、民間企業のGX投資支援(債務保証などの金融支援)、化石燃料賦課金や特定事業者負担金の徴収、排出量取引制度の運営など、多岐にわたる役割を担います。
事事業者に課される主な義務
GX推進法は、特に大量の温室効果ガスを排出する事業者に対し、以下の具体的な義務を課しています。
(1) GX推進戦略の策定・提出
・対象
年間のCO2直接排出量が10万トン以上の事業者(目安)が対象となります。
・内容
対象事業者は、自社の脱炭素化に向けた中長期的な目標、具体的な投資計画、技術開発の方向性、サプライチェーン全体での取り組みなどを盛り込んだ「GX推進戦略」を策定し、経済産業大臣に提出することが求められます。
・認定制度
提出されたGX推進戦略のうち、優れた計画は政府から認定を受け、GX経済移行債からの支援対象となるなど、優遇措置が適用される可能性があります。
これは、企業が脱炭素化を経営戦略の中核に据え、具体的な行動計画を示すことを促すものです。
(2) GX-ETS(排出量取引制度)への参加
・対象
2026年度から、年間CO2直接排出量が10万トン以上の企業は、排出量取引制度(ETS)への参加が実質的に義務付けられます。
・仕組み
対象事業者は、自社の排出量目標(プレッジ)を設定し、その達成状況を報告・開示します。
排出量目標に未達の場合、超過削減枠やカーボンクレジットの調達、または未達理由の説明が求められます。遵守しない事業者には、未履行分に上限価格の1.1倍の支払いが義務付けられる可能性があります。
排出削減が進み、排出枠に余剰が生じた場合は、市場で排出枠を売却できます。
(3) 炭素賦課金の支払い(間接的な影響)
・直接の対象
化石燃料の輸入事業者などが直接の対象となります。
・企業への影響
2028年度から導入される化石燃料賦課金は、化石燃料の価格に転嫁されることが想定されます。
これにより、エネルギー多消費産業を中心に、燃料コストの上昇という形で間接的な影響を受ける可能性があります。
企業は、このコスト増を見据え、省エネルギー化や再生可能エネルギーへの転換を加速させるインセンティブとなります。
まとめ
GX推進法は、日本が2050年カーボンニュートラルと経済成長を両立させるための、野心的かつ具体的なロードマップを示す法律です。
企業担当者は、この法律が定める「GX推進戦略の策定・提出」「GX-ETSへの参加」「炭素賦課金によるコスト増」といった義務と影響を深く理解し、自社の事業戦略に組み込むことが不可欠です。
脱炭素化への取り組みは、もはやコストではなく、企業価値向上と持続可能な競争力を確立するための重要な投資と捉えるべきです。
GX推進法を理解し、積極的に対応することで、企業は新たな成長機会を掴み、持続可能な社会の実現に貢献できるでしょう。
参考資料
経済産業省,「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定されました
https://www.meti.go.jp/press/2024/02/20250225001/20250225001.html
経済産業省, GX(グリーン・トランスフォーメーション)
https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/index.html
e-GOV,脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)
https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000032