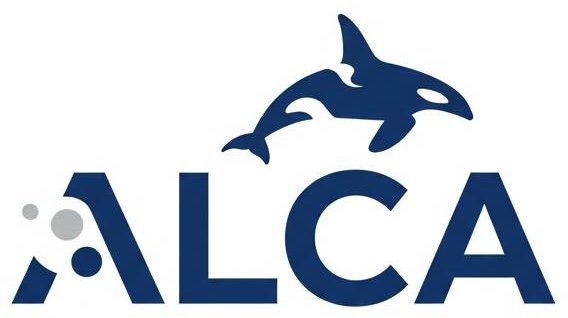はじめに
企業活動におけるエネルギー効率の向上と非化石エネルギーへの転換は、地球温暖化対策の推進、そして持続可能な経営を実現する上で不可欠な要素です。
日本において、これらの取り組みを法的に推進する根幹となるのが「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」(通称:省エネ法)です。
本記事では、企業の気候変動担当者向けに、省エネ法の概要、その全体像、そして企業に課される具体的な義務について、分かりやすく解説します。
省エネ法とは:法律の概要と目的
省エネ法は、1979年の第一次石油危機を契機に「エネルギーの使用の合理化に関する法律」として制定されました。その後、地球温暖化問題への対応やエネルギー安定供給の重要性が高まる中で、複数回にわたる改正を経て、現在の「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」という名称に至っています。
この法律の主な目的は、燃料資源の有効な利用を確保し、エネルギーの使用の合理化を総合的に推進すること、そして非化石エネルギーへの転換を促進することです。これにより、国民経済の健全な発展に寄与するとともに、地球温暖化対策にも貢献することを目指しています。
省エネ法は、エネルギーの「使用」に着目し、その効率的な利用を促すことで、温室効果ガス排出量の削減に貢献する、地球温暖化対策の基盤となる法律の一つです。
温対法(地球温暖化対策の推進に関する法律)が排出量報告を義務付けるのに対し、省エネ法は具体的なエネルギー使用の合理化を求める点で役割が異なります。
省エネ法の全体像:国・地方・事業者の役割
省エネ法は、国、地方公共団体、事業者、国民がそれぞれの立場でエネルギー使用の合理化と非化石エネルギーへの転換に取り組むことを求めています。その全体像は、以下の要素で構成されます。
1. 国の役割
・エネルギー使用の合理化に関する基本方針の策定
・特定事業者等に対する指導・助言、報告徴収、立ち入り検査
・機械器具等のエネルギー消費効率基準(トップランナー基準)の設定
・非化石エネルギーへの転換に関する目標設定や支援策の実施
2. 地方公共団体の役割
・地域の実情に応じたエネルギー使用の合理化に関する施策の実施
・事業者や住民への啓発活動
3. 事業者の役割
・エネルギー管理体制の構築
・エネルギー使用量の把握・記録・報告
・中長期的なエネルギー使用合理化計画の策定・実施
・非化石エネルギーへの転換努力
4. 国民の役割
・日常生活におけるエネルギー使用の合理化への協力
・エネルギー効率の高い製品の選択
このように、省エネ法は、エネルギーの供給側から需要側まで、幅広い主体に対してエネルギー効率の向上と非化石エネルギーへの転換を促す包括的な枠組みを提供しています。
事業者に課される主な義務
省エネ法は、事業者のエネルギー使用量に応じて、様々な義務を課しています。企業担当者として特に理解しておくべき主な義務は以下の通りです。
(1) 特定事業者・特定連鎖化事業者の義務
年間エネルギー使用量(原油換算)が一定規模以上(工場・事業場単位で1,500kL以上)の事業者、または複数の事業所を一体的に管理する連鎖化事業を営む事業者(特定連鎖化事業者)は、「特定事業者」として以下の義務が課されます。
・エネルギー管理統括者等の選任
エネルギー使用の合理化を推進するため、事業所ごとに「エネルギー管理統括者」および「エネルギー管理員」を選任し、国に届け出る義務があります。統括者は事業全体のエネルギー管理を統括し、管理員は具体的な実務を担当します。
・エネルギー使用状況の把握・記録
毎月、燃料、熱、電気の使用量や、それらに伴うエネルギー消費量を正確に把握し、記録する義務があります。これにより、エネルギー使用の実態を可視化し、削減目標設定の基礎とします。
・中長期計画の提出
エネルギー使用の合理化に関する中長期的な計画(5年間)を策定し、国に提出する義務があります。この計画には、エネルギー使用量の削減目標や具体的な対策内容を盛り込みます。
・定期報告書の提出
毎年度、前年度のエネルギー使用量、エネルギー消費原単位の状況、実施した省エネ対策の内容などをまとめた定期報告書を国に提出する義務があります。
・努力目標
特定事業者は、エネルギー消費原単位(生産量あたりのエネルギー消費量など)を年平均1%以上改善するよう努力する目標が課せられています。
(2) 特定荷主・特定連鎖化荷主の義務
年間貨物輸送量(トンキロ)が一定規模以上(3,000万トンキロ以上)の荷主、または複数の荷主事業を一体的に管理する連鎖化事業を営む荷主(特定連鎖化荷主)は、「特定荷主」として以下の義務が課されます。
・輸送に係るエネルギー使用状況の把握・記録
自社の貨物輸送に伴うエネルギー使用量を把握し、記録する義務があります。
・中長期計画の提出
輸送に係るエネルギー使用の合理化に関する中長期計画を策定し、国に提出する義務があります。
・定期報告書の提出
毎年度、輸送に係るエネルギー使用量やその合理化の状況をまとめた定期報告書を国に提出する義務があります。
(3) 特定輸送事業者・特定連鎖化輸送事業者の義務
年間エネルギー使用量(原油換算)が一定規模以上(鉄道、自動車、航空、船舶の各輸送モードで3,000kL以上)の輸送事業者、または複数の輸送事業を一体的に管理する連鎖化事業を営む輸送事業者(特定連鎖化輸送事業者)は、「特定輸送事業者」として以下の義務が課されます。
・輸送に係るエネルギー使用状況の把握・記録
自社の輸送事業に伴うエネルギー使用量を把握し、記録する義務があります。
・中長期計画の提出
輸送に係るエネルギー使用の合理化に関する中長期計画を策定し、国に提出する義務があります。
・定期報告書の提出
毎年度、輸送に係るエネルギー使用量やその合理化の状況をまとめた定期報告書を国に提出する義務があります。
(4) 建築物・機械器具等に関する義務
省エネ法は、工場や事業場だけでなく、建築物や特定の機械器具等にもエネルギー効率に関する義務を課しています。
・建築物
一定規模以上の新築・増改築を行う建築主に対し、建築物のエネルギー消費性能基準への適合を義務付けています。
・機械器具等(トップランナー制度)
自動車、家電製品、OA機器など、特定の機械器具等の製造事業者や輸入事業者に対し、最もエネルギー消費効率が高い製品の性能を目標値(トップランナー基準)として設定し、その達成を義務付けています。
まとめ
省エネ法は、企業のエネルギー使用の合理化と非化石エネルギーへの転換を強力に推進するための、多岐にわたる義務と支援策を定めた法律です。
企業担当者は、自社の事業規模や業態に応じて、特定事業者、特定荷主、特定輸送事業者などのいずれに該当するかを確認し、それぞれの義務を確実に履行する必要があります。
省エネ法への対応は、単なる法規制遵守に留まらず、エネルギーコストの削減、企業の環境イメージ向上、そして持続可能な社会の実現への貢献に繋がります。
本法律の趣旨を理解し、積極的にエネルギー効率の改善と非化石エネルギーへの転換に取り組むことが、企業の競争力強化に繋がるでしょう。
参考資料
経済産業省 資源エネルギー庁, 省エネ法の概要
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/overview/
経済産業省 資源エネルギー庁, 特定事業者向け情報
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/factory/procedure/
経済産業省 資源エネルギー庁, 輸送の省エネ法規制
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/transport/ninushi/
e-GOV,エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)
https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000049/