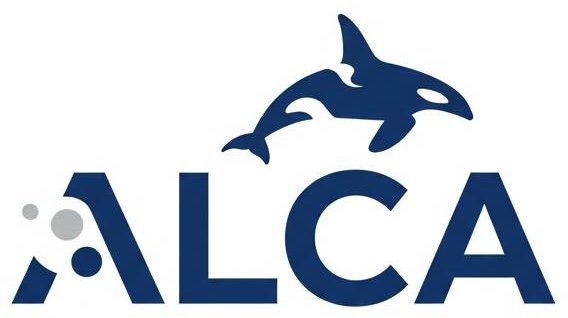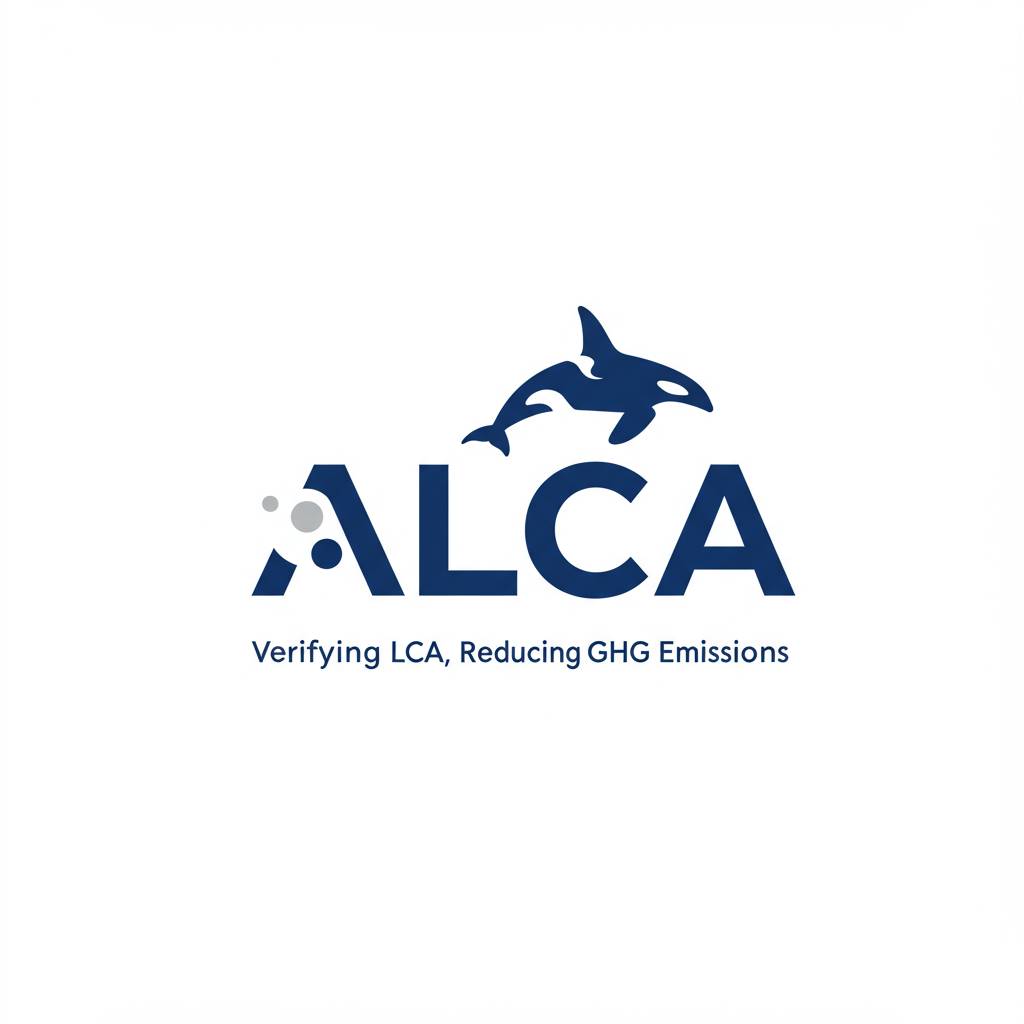はじめに
前回はGX-ETS(Green Transformation Emission Trading Scheme:排出量取引制度)における第三者検証の準備段階で企業が直面しがちな「つまずきやすいポイント」と、それを回避するための事前準備について解説いたしました。正確なデータ管理と適切な内部統制が、検証プロセスを円滑に進める上でいかに重要であるかをご理解いただけたことと存じます。
今回は、GX-ETS制度が今後どのように進化し、拡張・強化されていく可能性があるのか、その制度的進化の方向性について深掘りしてまいります。
GX-ETSはまだ発展途上の制度であり、将来的な変化を見据えて対応を検討することは、企業の脱炭素戦略を策定する上で不可欠です。初心者の方や企業の担当者の皆様が、このダイナミックな制度の未来像を明確に把握できるよう、キーワードである「フェーズ移行」「国全体制度」「業種拡大」を交えながら解説いたします。
GX-ETSの進化:フェーズ移行と本格化
GX-ETSは、2023年度から「フェーズ1」(試行期間)としてスタートし、2026年度からは「フェーズ2」(本格稼働)へと移行する計画が示されています。このフェーズ移行は、制度がより実効性を持ち、日本の脱炭素化を強力に推進するための重要なステップとなります。
1. フェーズ1(試行期間:2023年度~2025年度)
現在のフェーズ1は、制度の円滑な導入と運用に向けた準備期間と位置づけられています。参加企業は、自主的な排出量削減目標を設定し、その進捗を報告・開示することが求められます。この期間は、制度の仕組みを企業が理解し、排出量算定・報告体制を構築するための助走期間と言えるでしょう。排出枠の取引は行われますが、その有償化は限定的です。
2. フェーズ2(本格稼働:2026年度~)
2026年度からのフェーズ2では、GX-ETSは本格的な排出量取引制度へと移行します。この段階では、制度の対象となる企業が拡大し、排出枠の有償化(オークション)が導入される予定です。
排出枠に明確な金銭的価値が付与されることで、企業は排出量削減へのインセンティブをより強く感じ、市場メカニズムを通じた効率的な削減が促進されることが期待されます。
この本格稼働は、企業にとって排出量削減が単なる環境対策に留まらず、直接的に財務に影響を与える経営課題となることを意味します。排出枠の購入コストや、超過削減枠の売却益が、企業の収益に影響を与えるため、より戦略的な排出量管理が求められるようになります。
国全体制度としての発展
GX-ETSは、将来的には日本全体の脱炭素化を推進する中核的な国全体制度へと発展していく可能性を秘めています。
現在、GX-ETSは「自主的な排出量取引制度」として位置づけられていますが、GX推進法に基づく炭素賦課金制度や、GX経済移行債の活用など、他のGX関連施策と連携しながら、より広範な企業や経済活動を巻き込む制度へと進化していくことが見込まれます。
・炭素賦課金制度との連携
炭素賦課金は、化石燃料の輸入事業者等に課されるものであり、排出量取引制度とは異なるアプローチで炭素価格を形成します。GX-ETSがこの炭素賦課金制度とどのように連携し、日本全体の炭素価格メカニズムを構築していくのかは、今後の重要な論点となります。
・GX経済移行債の活用
GX経済移行債は、脱炭素化に向けた投資を支援するための財源であり、GX-ETSの収益もこの財源の一部となる可能性があります。制度が拡大し、収益が増加することで、脱炭素技術開発や設備投資への支援が強化され、日本全体のGX推進が加速することが期待されます。
このように、GX-ETSは単独の制度としてではなく、GX全体戦略の中核を担う国全体制度として、その役割を拡大していくことでしょう。
業種拡大と対象範囲の深化
GX-ETSの対象範囲は、今後さらに拡大していくことが見込まれます。
・業種拡大
現在、GX-ETSの参加企業は、電力、鉄鋼、化学などの主要な排出源を持つ業種が中心ですが、将来的にはより多くの業種拡大が検討される可能性があります。特に、排出量が多いものの、現行制度の対象外となっている業種や、サプライチェーン全体での排出量削減が求められる業種への適用が議論されることでしょう。
・中小企業への影響
制度の本格化に伴い、直接的な対象企業だけでなく、そのサプライチェーンに連なる中小企業にも排出量削減の要請が波及していくことが予想されます。大企業からの排出量データ開示要請や、サプライチェーン排出量(スコープ3)削減への協力要請が増加することで、中小企業もGX-ETSの間接的な影響を受けることになります。
・対象範囲の深化
排出量算定・報告の対象範囲が、より詳細化・厳格化される可能性もあります。例えば、現行では算定が難しいとされている特定の排出源や、バイオマス燃料の排出量算定方法など、より精緻なルールが導入されることが考えられます。
これらの変化は、企業にとって新たな機会と同時に、より高度な排出量管理能力を求めることになります。
まとめ
GX-ETSは、フェーズ移行を経て本格稼働し、将来的には日本全体の脱炭素化を推進する中核的な国全体制度へと発展していくことが見込まれます。
その過程で、業種拡大や対象範囲の深化が進み、より多くの企業が制度の影響を受けることになります。企業は、これらの制度的進化の方向性を早期に把握し、排出量管理体制の強化、削減戦略の策定、そして新たなビジネス機会の創出に取り組むことが不可欠です。
次回は、海外の主要な排出量取引制度(EU-ETS、中国ETSなど)と日本のGX-ETSとの違いについて、国際的な視点から比較解説してまいります。GX-ETSへの対応でお困りの際は、経済産業省のGX-ETSにおける第三者検証機関として登録されている弊社が、皆様の制度対応を強力にサポートいたします。次回以降の解説にご期待ください。
当社は、経済産業省のGX-ETSにおける第三者検証機関として登録されており、独立した第三者検証機関としてGX-ETSにおける排出量実績報告をサポートいたします。
GX-ETS第三者検証サービスの詳細はこちらをご覧ください。
GX-ETS 第三者検証サービス
お客様が算定・報告されたGHG排出量データが、GX-ETSのガイドラインや国際基準(ISO 14064-3など)に準拠しているかを客観的に評価・確認します。
また、GX-ETSへの対応でお困りの際は、当社までお気軽にご連絡ください。
お問い合わせ参考資料
経済産業省「GXリーグ公式サイト:排出量取引制度(GX-ETS)」
https://gx-league.go.jp/action/gxets/
内閣官房GX実行会議資料「GX実行に向けた基本方針」
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/gx_jikkou_kaigi/index.html