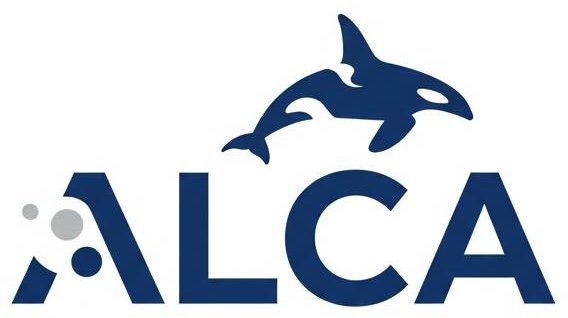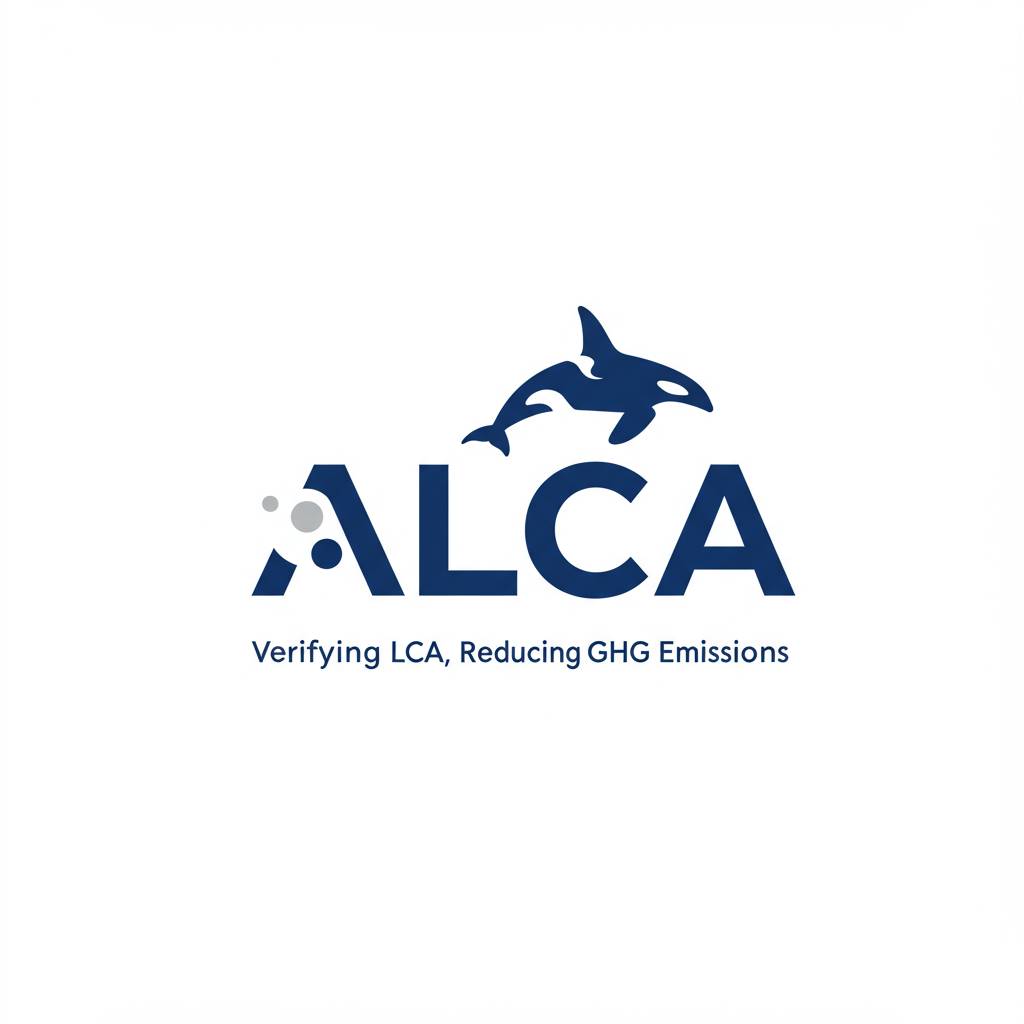はじめに
前回は、GX-ETS(Green Transformation Emission Trading Scheme:排出量取引制度)が今後どのように進化し、拡張・強化されていく可能性があるのか、その制度的進化の方向性について解説いたしました。フェーズ移行や国全体制度としての発展、業種拡大といった見通しをご理解いただけたことと存じます。
今回は、視点を国際的なものに移し、EUや中国など海外の主要な排出量取引制度(ETS)と日本のGX-ETSとの比較を通じて、日本企業への示唆を整理してまいります。
グローバル動向を把握し、各国の制度が企業の競争環境や炭素価格に与える影響を理解することは、国際的なビジネスを展開する上で不可欠です。国際的な脱炭素化の潮流と日本の立ち位置を明確に把握できるよう、詳しく解説いたします。
世界の排出量取引制度(ETS)の現状
現在、世界では多くの国や地域で排出量取引制度が導入されており、その数と規模は年々拡大しています。これらの制度は、それぞれ異なる設計思想や運用状況を持ちながらも、市場メカニズムを通じて温室効果ガス排出量の削減を促すという共通の目的を持っています。
主要なETSとして、EU-ETS(欧州連合排出量取引制度)と中国ETSが挙げられます。これらは、その規模や歴史、特徴において、日本のGX-ETSと比較する上で重要なベンチマークとなります。
EU-ETS(欧州連合排出量取引制度)の特徴
EU-ETSは、2005年に導入された世界で最も歴史が長く、成熟した排出量取引制度です。
現在、GX-ETSは「自主的な排出量取引制度」として位置づけられていますが、GX推進法に基づく炭素賦課金制度や、GX経済移行債の活用など、他のGX関連施策と連携しながら、より広範な企業や経済活動を巻き込む制度へと進化していくことが見込まれます。
・歴史と成熟度
20年近い運用実績を持ち、複数回の制度改革を経て、その仕組みは非常に洗練されています。対象となる排出源も広範であり、電力、熱供給、エネルギー集約型産業(鉄鋼、セメント、化学など)、さらには航空分野も含まれます。
・炭素価格
EU-ETSの最大の特徴は、その高い炭素価格です。排出枠の供給量を厳しく制限し、オークションによる有償化を積極的に進めることで、高い炭素価格が形成されています。この高い炭素価格は、企業に強力な排出量削減インセンティブを与え、脱炭素技術への投資を促しています。
・有償化の進展
排出枠のほとんどがオークションを通じて有償で取引されており、企業は排出量に応じてコストを負担します。これにより、排出量削減が直接的な経済的メリットに繋がる構造が確立されています。
・CBAM(炭素国境調整メカニズム)との関連
EUは、域外からの輸入品に炭素コストを課すCBAMの導入を進めています。これは、EU域内の企業が排出量取引制度によって負担する炭素コストと、域外企業のコストとの間の不公平を是正し、競争環境の公平性を保つことを目的としています。CBAMは、EUに製品を輸出する日本企業にも大きな影響を与える可能性があります。
中国ETS(全国炭素排出権取引市場)の特徴
中国ETSは、2021年に全国規模で本格稼働を開始した、世界最大の排出量取引市場です。
・規模と特徴
対象となる排出量は世界最大規模であり、中国の脱炭素化目標達成に向けた重要なツールと位置づけられています。
・対象範囲
現在は電力セクターが主な対象ですが、将来的には他の産業セクターへの拡大も検討されています。
・炭素価格
EU-ETSと比較すると、現在のところ炭素価格は比較的低い水準にあります。これは、制度がまだ発展途上であることや、経済成長とのバランスを考慮しているためと考えられます。
・発展途上
比較的新しい制度であり、運用経験を積みながら、今後さらに制度設計や市場機能が強化されていくことが予想されます。
日本版GX-ETSの特徴と国際比較からの示唆
日本のGX-ETSは、2023年度から試行期間が始まり、2026年度から本格稼働を目指す、比較的新しい制度です。
・自主性からのスタート
フェーズ1では、企業が自主的に参加し、削減目標を設定する「自主的排出量取引制度」としてスタートしました。これは、企業が制度に慣れ、排出量管理体制を構築するための段階的なアプローチと言えます。
・炭素価格
現時点では排出枠の有償化は限定的であり、本格的な炭素価格の形成はフェーズ2以降となります。将来的には、EU-ETSのような高い炭素価格を目指すのか、あるいは中国ETSのような段階的なアプローチを取るのか、その動向が注目されます。
・対象範囲
主要な排出源を持つ業種が中心ですが、今後業種拡大の可能性も示唆されています。
・GX推進法との連携
GX-ETSは、炭素賦課金制度やGX経済移行債など、GX推進法に基づく他の施策と一体的に推進される点が特徴です。これは、日本独自のグローバル動向への対応であり、多角的なアプローチで脱炭素化を目指すものです。
日本企業への示唆
海外のETSとの比較から、日本企業は以下の重要な示唆を得ることができます。
1. グローバル動向の継続的な把握
世界の排出量取引制度は常に進化しており、各国の政策や市場の動向は、日本企業の国際的な競争環境に直接影響を与えます。EUのCBAMのように、貿易に影響を及ぼす制度も登場しており、常に最新のグローバル動向を把握し、自社の事業戦略に反映させることが不可欠です。
2. 炭素価格変動への備え
海外で事業を展開する企業は、現地の高い炭素価格が事業コストに与える影響を考慮する必要があります。また、国内のGX-ETSも本格稼働後は炭素価格が形成されるため、国内事業においても炭素コストを織り込んだ経営計画が求められます。排出量削減への投資は、将来的な炭素コスト上昇リスクへのヘッジともなり得ます。
3. 国際的な競争力維持のための脱炭素化投資
EU-ETSのような高い炭素価格が形成されている地域では、企業は脱炭素技術への投資を加速させています。日本企業も、国際的な競争環境で優位性を保つためには、排出量削減に向けた積極的な投資や技術開発が不可欠です。これは、単なるコストではなく、新たなビジネス機会や企業価値向上に繋がる戦略的な投資と捉えるべきです。
4. サプライチェーン全体での排出量削減
多くの海外ETSや国際的なイニシアティブは、サプライチェーン全体での排出量削減(スコープ3)を重視する傾向にあります。日本企業も、自社だけでなく、サプライヤーや顧客との連携を通じて、サプライチェーン全体の脱炭素化に取り組むことが、国際的な評価を高める上で重要となります。
まとめ
GX-ETSは、EU-ETSや中国ETSといった世界の主要な排出量取引制度と比較すると、その歴史や成熟度、炭素価格の形成において異なる特徴を持っています。しかし、グローバル動向として脱炭素化の潮流は加速しており、日本企業はこれらの国際的な制度や競争環境の変化を深く理解し、自社の脱炭素戦略に組み込むことが不可欠です。
次回は、GX-ETS制度が企業価値に与える影響について、炭素が財務に与える意味や、ESG評価との関連性といった視点から解説してまいります。GX-ETSへの対応でお困りの際は、経済産業省のGX-ETSにおける第三者検証機関として登録されている弊社が、皆様の制度対応を強力にサポートいたします。次回以降の解説にご期待ください。
当社は、経済産業省のGX-ETSにおける第三者検証機関として登録されており、独立した第三者検証機関としてGX-ETSにおける排出量実績報告をサポートいたします。
GX-ETS第三者検証サービスの詳細はこちらをご覧ください。
GX-ETS 第三者検証サービス
お客様が算定・報告されたGHG排出量データが、GX-ETSのガイドラインや国際基準(ISO 14064-3など)に準拠しているかを客観的に評価・確認します。
また、GX-ETSへの対応でお困りの際は、当社までお気軽にご連絡ください。
お問い合わせ参考資料
経済産業省「GXリーグ公式サイト:排出量取引制度(GX-ETS)」
https://gx-league.go.jp/action/gxets/
内閣官房GX実行会議資料「GX実行に向けた基本方針」
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/gx_jikkou_kaigi/index.html