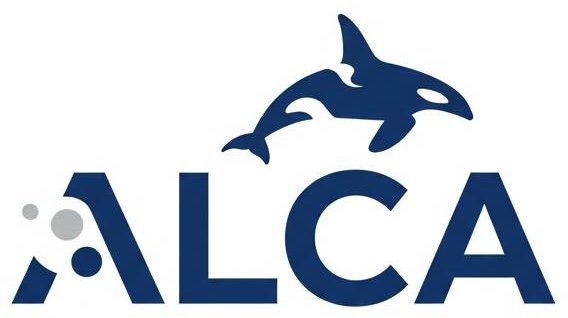はじめに
これまでの記事で、LCA(ライフサイクルアセスメント)が企業の環境戦略においていかに重要であるかを解説してきました。
世界的な脱炭素社会への移行が加速する中、各国・地域では環境規制が急速に強化されており、企業はこれに対応することが喫緊の課題です。
特に、製品のライフサイクル全体にわたる環境負荷の情報開示や削減を求める動きが顕著になっています。
本記事では、日本の「グリーン調達法」における公共調達の動き、EUが主導するデジタル製品パスポート(DPP)の導入、そして建築物ライフサイクルカーボン(LCCO2)の算定・評価といった最新の規制動向が、企業にどのような影響を与え、どのような具体的施策が求められているのかを解説します。
日本の「グリーン調達法」と公共調達の推進
日本には「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(通称:グリーン購入法)があり、国や地方公共団体が環境負荷の少ない製品・サービスを優先的に調達することを義務付けています。これは、政府機関が率先して環境配慮型製品の需要を創出し、市場全体のグリーン化を促すことを目的としています。
・グリーン調達法の目的とLCAの関連性
グリーン調達法は、製品のライフサイクル全体を考慮した環境配慮を促すものであり、LCAの考え方がその根底にあります。
例えば、再生材の利用率、省エネルギー性能、廃棄時のリサイクル性などが評価項目となり、これらの情報はLCAによって定量的に裏付けられます。
・企業への影響
公共調達をビジネスとする企業にとっては、自社製品やサービスがグリーン調達法の基準を満たしていることが、競争力を維持・強化する上で不可欠です。
将来的には、製品のCFPデータなど、より詳細な環境情報開示が求められる可能性も高まります。
デジタル製品パスポート(DPP)の導入と企業への影響
DPPは、製品のライフサイクル全体にわたる詳細な情報をデジタル形式で記録・共有する仕組みです。
EUが循環経済行動計画の一環として導入を進めており、2024年以降、バッテリーを皮切りに、繊維、電子機器、建設資材など、順次対象製品が拡大される見込みです。
・DPPの目的と機能
DPPの主な目的は、製品のトレーサビリティと透明性を確保し、循環経済の実現を加速させることです。
製品の原材料、製造プロセス、修理可能性、リサイクル性、そしてLCAで算定されたCFPなどの環境負荷データがDPPを通じて情報開示されます。
これにより、消費者や企業は製品の環境性能を容易に確認できるようになります。
DPPの詳細についてはこちら:デジタル製品パスポート(DPP)とは?事業者が知るべき全体像と義務
・企業への影響と対応
DPPの導入は、企業に製品ごとのLCAデータ整備と、そのデジタル化を強く求めます。
サプライチェーン全体でデータを連携し、リアルタイムで更新できるシステムの構築が不可欠となるでしょう。
これは、単なる情報開示の義務化に留まらず、製品設計からサプライチェーン管理、顧客とのコミュニケーションまで、ビジネスプロセス全体の見直しを促すものです。
・建築物LCA(ホールライフカーボン:WLC)の最新動向と企業への影響
建築分野は、その建設から運用、解体に至るライフサイクル全体で多大なCO2を排出するため、脱炭素化が喫緊の課題です。
従来の運用段階のCO2排出量(オペレーショナルカーボン)だけでなく、建材製造や建設、解体に伴う「エンボディドカーボン」を含むライフサイクル全体でのCO2排出量(ホールライフカーボン)の算定・評価が重要視されています。
・LCCO2の評価範囲
LCCO2は、原材料の調達・製造・輸送・施工(A区分)、運用・維持管理(B区分)、解体・廃棄(C区分)の各段階で発生するCO2排出量を評価します。
さらに、解体後の再利用・リサイクルによる排出削減ポテンシャル(D区分)も考慮されることがあります。
・国内外の規制動向
EUでは、2028年から1,000㎡を超える新築建築物に対し、LCCO2の算定・公表が義務化される見込みです。
日本でも、国土交通省が2028年度を目途に建築物LCAの実施を促進する制度の開始を目指すことを決定しており、J-CAT(建築物ホールライフカーボン算定ツール)やCASBEE(建築環境総合性能評価システム)といったツールを活用した算定が推進されています。
・企業への影響と対応
建築関連企業は、設計段階での環境配慮型資材の選択、施工方法の工夫、長寿命化設計、解体時のリサイクル計画など、LCCO2削減に向けた具体的な取り組みが求められます。
LCCO2の算定能力を構築し、その結果を情報開示することで、環境配慮型建築物としての競争優位性を確立できるでしょう。
まとめと次のステップ
グリーン調達法の推進、DPP導入、そして建築物LCAの推進といった最新の規制動向は、企業に対し、製品や事業活動のライフサイクル全体にわたる環境負荷の正確な把握と、その情報開示を強く求めています。
特にCFPは、これらの取り組みの共通言語として、その重要性を増しています。これは、単なるコンプライアンス対応に留まらず、企業の脱炭素戦略の中核をなし、持続可能なビジネスを確立するための重要な要素となります。
次回は、これらの最新の動きを踏まえ、LCAで先行するために企業が取るべき具体的な一手について、より実践的な視点から解説します。
参考文献
経済産業省、カーボンフットプリントレポート
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/carbon_footprint/pdf/20230331_2.pdf
経済産業省、カーボンフットプリントガイドライン
https://www.env.go.jp/content/000124385.pdf
日本貿易振興機構(ジェトロ)、EU
循環型経済関連法の最新概要
エコデザイン規則、修理する権利指令、包装・包装廃棄物規則案
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/01/e2a3dada17af22e3/20240023_01.pdf
環境省、グリーン購入法について(グリーン購入法.net)
https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/
国土交通省、建築物のライフサイクルカーボンの算定・評価等を促進する制度に関する検討会
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk4_000302.html