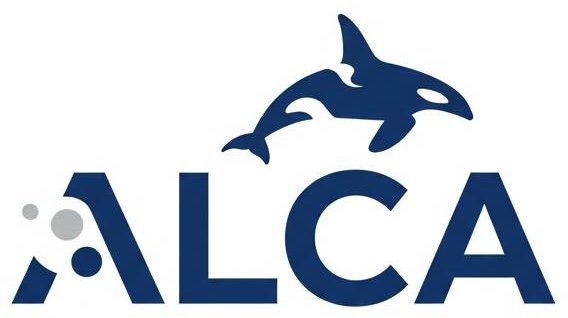はじめに
本章では、建築物のLCAの動向について、国内外の動向を解説し、その後、具体的な算定方法、実施することによる企業のメリット、活用可能な制度等についてご紹介します。
背景と概要
建築物のライフサイクル全体(資材製造、建設、運用、維持保全、解体・廃棄)を通じて排出される二酸化炭素(LCCO2)の削減は、2050年カーボンニュートラル実現に向けた国際的な喫緊の課題です。
世界各国、特に欧州を中心に、建築物のエネルギー消費(運用時CO2)だけでなく、建設や解体に伴うCO2排出(エンボディドカーボン)を含むLCCO2全体を評価・削減する動きが加速しています。
これは、パリ協定に基づく各国の温室効果ガス削減目標達成に不可欠であり、不動産分野における気候変動リスクへの対応や、投資家からのESG(環境・社会・ガバナンス)に関する要請の高まりも背景にあります。
国際的な主要動向
国際的な建築物LCCO2削減の取り組みは、主に規制強化、市場メカニズム、評価・情報開示フレームワークの発展という形で進展しています。
| 国・地域 | 主な取組 |
|---|---|
| 欧州連合(EU) |
EUでは、建築物のエネルギー性能指令(EPBD)の改正などを通じて、建築物のライフサイクル全体での炭素排出量削減義務化に向けた動きが進んでいます。
特に、2028年からは、1,000㎡を超える新築建築物を対象に、ライフサイクルカーボンの算定・公表が義務付けられる見込みです。これは、域内の建築部門における脱炭素化を加速させる重要なステップです。 さらに、EUの一部の国では、既にライフサイクルカーボン排出量の上限値を設定する規制を導入しており、より直接的に削減を促しています。 |
| 北欧 |
北欧諸国では、建設・建築分野における循環型原則の統合が進められています。これは、建築材料の再利用やリサイクルを促進し、建設段階でのCO2排出量(エンボディドカーボン)を削減することを目的としています。
建築物の長寿命化や解体材の有効活用など、ライフサイクル全体での資源効率と炭素効率を高めるアプローチが重視されています。 |
| 米国 | 米国も連邦政府の建物における排出量削減目標を設定するなど、公共部門を中心に脱炭素化を推進しています。また、州や市レベルでの建築物エネルギーコード強化や、低炭素建材の利用促進に向けた取り組みも見られます。 |
| 中国 | 世界最大のCO2排出国の一つである中国は、建築部門を含む各産業での排出削減目標を設定し、省エネ基準の強化や再生可能エネルギーの導入拡大を進めています。 |
市場メカニズムと評価フレームワーク
不動産市場においては、気候変動関連の財務情報開示タスクフォース(TCFD)の提言や、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)による開示基準(IFRS S2号)などが、企業のバリューチェーン全体での温室効果ガス排出量(Scope 3を含む)の開示を求めています。
建築物の建設・維持保全・解体に伴う排出は、不動産事業者のScope 3排出量の重要な部分を占めるため、LCCO2の算定と削減への取り組みが企業価値評価に直結するようになっています。
また、不動産セクターの環境性能評価ツールであるGRESBや、不動産の気候変動移行リスク分析ツールであるCRREMなどが、LCCO2評価を組み込むなど、国際的なイニシアティブが協調した動きを見せており、投資家や金融機関が不動産の環境性能を評価する上で重要な役割を果たしています。
企業は、これらの評価フレームワークへの対応を通じて、国際的な競争力を維持・強化する必要があります。
日本のLCCO2削減に向けた取り組み
日本は、2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指しており、国内の最終エネルギー消費量の約3割を占める建築物分野の脱炭素化が不可欠です。これまでの省エネ施策に加え、ライフサイクル全体でのCO2排出削減に取り組む必要性が認識されています。
政策目標
2050年までに住宅・建築物のストック平均でZEH・ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス/ビルディング)基準の水準の省エネルギー性能確保を目指すとともに、2030年度以降新築される住宅・建築物については、ZEH・ZEB基準の水準の省エネルギー性能確保を目指しています。
また、建築物省エネ法に基づき、2025年度からは原則全ての新築住宅・建築物に対して省エネ基準適合が義務付けられます。
LCCO2算定・評価の推進:建築物使用時のエネルギー消費に伴うCO2排出(オペレーショナルカーボン)に加え、資材製造、建設、維持保全、解体に伴うCO2排出(エンボディドカーボン)を合わせたライフサイクルカーボン全体の削減が課題となっています。
国内の分野別CO2排出量において、建築物のライフサイクルカーボンは約4割を占めると推定されています。
算定ツールの開発
産官学連携による「ゼロカーボンビル推進会議」での検討を経て、建築物のライフサイクルカーボン算定ツール(J-CAT)が開発され、2024年10月に公開されました。これにより、建築物のライフサイクル全体を通じたCO2排出量の算定・評価が可能となります。
J-CATのケーススタディ平均値(全用途、N=26)によると、ライフサイクルカーボンの構成比はオペレーショナルカーボン52%、エンボディドカーボン48%となっています。
制度化への検討
建築物LCCO2の実施を促す制度の開始を2028年度を目途に目指しており、算定方法の統一化、支援制度の検討、公共建築物での先行実施などが進められています。
現時点では制度の詳細は検討段階ですが、新築非住宅で2,000㎡以上の建物はライフサイクルカーボンの算定が義務化される可能性が指摘されています。
先行事例
不動産事業者が先行してライフサイクルカーボンの算定に取り組み始めており、2022年には業界団体(一般社団法人不動産協会)で建設時GHG排出量算定マニュアルを作成するなど、国内での取り組みも進んでいます。
課題と今後の展望
建築物LCCO2の評価と削減には、共通の算定基準やデータ基盤の整備、特にエンボディドカーボンに関する信頼性の高いデータ(建材ごとのCO2原単位など)の不足、サプライチェーン全体での協働の必要性など、依然として多くの課題が存在します。
しかし、国際的な規制強化の動きや、金融市場からの要請の高まり、技術開発の進展などを背景に、今後はLCCO2評価の標準化、建材の環境性能表示の普及、循環型建築の推進、デジタル技術(BIMなど)を活用したLCCO2管理などがさらに加速すると考えられます。
建築部門の脱炭素化は、単なる環境対策に留まらず、新たなビジネス機会や競争力の源泉となるでしょう。
参考文献
国土交通省、建築物のライフサイクルカーボンの算定・評価等を促進する制度に関する検討会
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk4_000302.html
一般財団法人住宅・建築SDGs推進センター/一般社団法人日本サステナブル建築協会、令和4年度ゼロカーボンビル(LCCO2ネットゼロ)推進会議報告書
https://www.ibecs.or.jp/zero-carbon_building/files/230515_document.pdf
国土交通省/OECD、ゼロカーボン建築ライフサイクル CO2
の削減に向けた世界の動向
https://www.ibecs.or.jp/topic/pdf/j-oecd_seminar_j.pdf
環境省、国内外の最近の動向について(報告)(2024)
https://www.env.go.jp/content/000198600.pdf