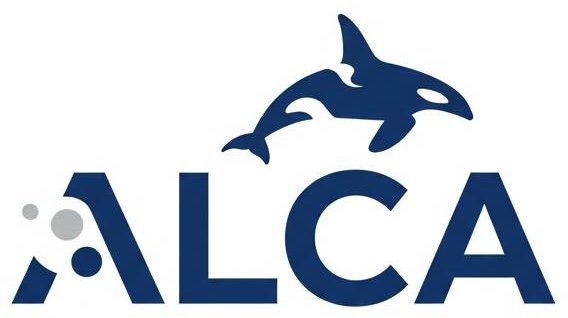はじめに
これまでの記事では、建築物LCAや建築物ライフサイクルカーボンの背景についてご紹介しました。
本記事では、建築物のライフサイクル全体にわたるCO2排出量、すなわちライフサイクルカーボン(LCCO2)の算定・評価の重要性と、実際の算定をするためのツールについてご紹介します。
はじめに:ライフサイクルカーボン(LCCO2)の重要性
2050年カーボンニュートラルの実現は、世界共通の喫緊の課題であり、建築分野もその達成に不可欠な役割を担っています。
従来、建築物の環境負荷評価は、建物の運用段階におけるエネルギー消費、すなわちオペレーショナルカーボン(OC)に焦点が当てられることが一般的でした。
しかし、建築活動全体が地球環境に与える影響を正確に把握し、真の脱炭素社会を実現するためには、建物の建設、使用、そして解体に至るまでの「ゆりかごから墓場まで」のライフサイクル全体で発生する温室効果ガス(GHG)排出量、特に二酸化炭素(CO2)排出量、すなわちライフサイクルカーボン(LCCO2)を包括的に評価することが不可欠です。
欧米を中心に、建築物のライフサイクル全体を通じたCO2削減に向けた取り組みが加速しており、国際標準化機構(ISO)やWorld Green Building Council (WGBC)などでも評価方法に関する議論が進んでいます。
日本においても、このような国際的な動向を踏まえ、国土交通省を中心に建築物のライフサイクル全体での環境負荷低減を目指す動きが活発化しています。
ライフサイクルカーボンの評価範囲は、一般的に以下の区分に分けられます。
| A区分(アップフロントカーボン) | 原材料の調達、製造、輸送、建設現場での施工段階で発生する排出量。 |
|---|---|
| B区分(オペレーショナルカーボンと使用段階の資材関連排出量) | 建物使用中のエネルギー消費(光熱水)による排出量(オペレーショナルカーボン)に加え、維持保全、修繕、交換、改修に伴う資材製造や輸送、施工などで発生する排出量。 |
| C区分(エンドオブライフカーボン) | 建物解体・撤去、廃棄物の輸送、中間処理、最終処分に伴う排出量。 |
| D区分(ポテンシャルリユース・リカバリー) | 解体された資材の再利用やリサイクルによるポテンシャルな排出削減量(算定対象に含めるかは任意)。 |

図.ライフサイクルカーボンの枠組み
LCCO2の算定・評価は、設計段階での環境配慮型資材の選択や、施工方法の工夫、長寿命化設計、解体時のリサイクル計画などに繋がる重要なプロセスとなります。
建築物LCCO2の算定・評価アプローチ
算定対象とするライフサイクル段階をどこまで含めるかによって、評価の範囲が異なります。包括的なLCCO2評価を目指す場合、前述のISO区分AからCまでを対象とすることが一般的です。
特に、資材製造や施工段階で発生するアップフロントカーボンは、建物の種類や構造、使用する資材によって大きく変動するため、この段階の評価は脱炭素設計において非常に重要です。
算定にあたっては、金額ベースではなく数量ベースで評価することが推奨されます。これは、資材の価格変動に左右されず、実際の物理的な活動量に基づいた排出量を把握できるため、環境負荷低減のための設計や施工における「努力」がより正確に反映されるためです。
例えば、再生材を多く含む資材や、製造時のエネルギー消費が少ない資材を選択した場合、数量ベースで評価することでその環境負荷低減効果が明確になります。
しかし、LCCO2算定にはいくつかの課題も存在します。特に、建物を構成する多種多様な資材や設備に関する網羅的で信頼性の高い排出原単位データベースの整備が求められます。また、算定方法の標準化や透明性の確保も重要な課題であり、これらの課題を克服するための取り組みが進められています。
建築物ホールライフカーボン算定ツール「J-CAT」
このような背景のもと、日本国内における建築物のLCCO2算定・評価を促進するために開発されたのが、「建築物ホールライフカーボン算定ツール(J-CAT/Japan Carbon Assessment Tool for Building Lifecycle)」です。
J-CATは、一般財団法人住宅・建築SDGs推進センター(IBECs)内に2022年12月に設置されたゼロカーボンビル(LCCO2ネットゼロ)推進会議における産官学連携の検討を経て開発されました。
J-CATの目的は、建築物の建設から解体に至るまでの生涯にわたるCO2排出量を定量的に評価し、脱炭素設計や環境配慮型建築の普及を支援することです。当面の算定対象は非住宅および集合住宅となっています。
J-CATは、インターネットを通じて無料で提供されており、IBECsのウェブサイトで利用登録を行うことで誰でもダウンロードして使用することができます。
ツールはExcelシート形式で提供されており、ユーザーは建設資材の数量や建物の仕様に関する情報を入力することで、自動的にLCCO2排出量が計算される仕組みとなっています。これにより、専門家だけでなく、より多くの建築関係者がLCCO2算定に取り組むことが可能になります。
J-CATの主な特徴と機能
J-CATには、建築物のLCCO2算定を効率的かつ包括的に行うためのいくつかの特徴があります。
1. ホールライフカーボンの包括的算定
J-CATは、ISOの表記区分に準拠し、資材製造・施工段階(A区分)、使用段階(B区分)、解体段階(C区分)におけるCO2排出量を算定することができます。これにより、建物の「ゆりかごから墓場まで」の環境負荷を網羅的に評価することが可能です。ただし、解体後の再利用やリサイクルといったD区分については、将来的な算定対象への含めることが検討されています。
2. 数量ベースでの算定
金額に依存せず、建設資材の物量など実際の活動量に基づいてCO2排出量を算定します。これにより、資材の選択や設計・施工における環境配慮の取り組みが排出量削減効果として直接的に反映され、より正確な評価が可能となります。
3. 活用目的に合わせた3つの算定法
J-CATでは、ユーザーの算定の目的や詳細度に応じて選択できる3つの算定方法が提供されています。これにより、概略的な評価から詳細な評価まで、多様なニーズに対応することができます。
4. 詳細な算定結果表示
算定結果は、グラフや表を用いて分かりやすく表示されます。これにより、LCCO2排出量の内訳や各ライフサイクル段階での排出割合などを視覚的に把握することができ、環境負荷低減のための具体的な改善点の特定に役立ちます。
J-CATの正式版は、試行版での知見やフィードバックを反映し、2024年10月31日に公開されました。その後も、2024年12月17日には計算ソフトウェアの不具合を修正したバージョンが配布されるなど、継続的な改善が行われています。
J-CATの活用事例と今後の展望
J-CATは、公開以降、建築設計事務所や建設会社などで活用が進んでいます。例えば、東急建設では、新築工事におけるCO2排出量算定にJ-CATを導入し、その有効性を確認しています。
J-CATで算定されたデータは、異なる建築プロジェクト間での比較や、同一プロジェクトにおける設計変更による排出量削減効果の検証などに活用することが可能です。これにより、より環境性能の高い建築物の普及促進に貢献することが期待されます。
今後の展望としては、前述のD区分を含めた算定範囲の拡充や、より網羅的で信頼性の高い排出原単位データベースの整備などが挙げられます。また、他の建築関連ツールやBIM(Building Information Modeling)との連携なども進めば、LCCO2算定の効率化と精度向上に大きく貢献するでしょう。
J-CATは、日本における建築分野の脱炭素化に向けた重要なツールとして、その機能拡充と普及が期待されています。
まとめ
建築物のライフサイクル全体で発生するLCCO2の算定・評価は、2050年カーボンニュートラル実現に向けた建築分野の重要な取り組みです。
J-CATは、このLCCO2算定を支援するために日本で開発された無料ツールであり、ホールライフでの算定、数量ベースでの評価、複数の算定法選択、詳細な結果表示といった特徴を持っています。既に実務での活用が始まっており、今後の普及と機能拡充により、建築分野の脱炭素化に大きく貢献することが期待されます。
参考文献
国土交通省、建築物のライフサイクルカーボンの算定・評価等を促進する制度に関する検討会
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk4_000302.html
一般財団法人住宅・建築SDGs推進センター、建築物ホールライフカーボン算定ツール(J-CAT®)
https://www.ibecs.or.jp/zero-carbon_building/jcat/index.html
東急建設株式会社、一般公開ツール『J-CAT』により建築工事(新築)のCO2排出量を算定
https://www.tokyu-cnst.co.jp/topics/2627.html