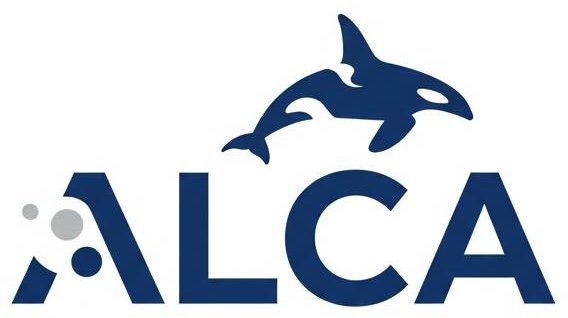はじめに
前回の記事では、LCA(ライフサイクルアセスメント)における最も代表的な指標として「カーボンフットプリント(CFP)」をご紹介し、製品やサービスの一生を通じて排出されるCO2をいかに把握するかが重要であるかを解説しました。
しかし、企業の環境への取り組みを考えたとき、「CO2排出量さえ減らせば、それで万事OK」なのでしょうか?
答えは「ノー」です。
地球環境が抱える課題は、温暖化だけではありません。
今回は、LCAが評価するCO2以外の重要な環境インパクト指標、特に「資源」「水資源」「生態系」への影響に焦点を当て、なぜそれらがビジネスにとって重要なのかを掘り下げていきます。
なぜCO2以外の指標も重要なのか?
環境問題は、それぞれが複雑に絡み合っています。
例えば、ある製品のCO2排出量を減らすために、特定の代替材料に切り替えたとします。
しかし、その材料を採掘・生産する過程で、希少な資源を大量に使ったり、地域の水資源を枯渇させてしまったり、あるいは地域の生態系を破壊してしまうかもしれません。
CFP以外の主要なインパクト指標
LCAでは、「環境影響領域」と呼ばれるカテゴリーごとにインパクトを評価します。
ここでは、ビジネスへの影響も大きい代表的な指標をいくつか見ていきましょう。
1. 資源消費
評価する指標の例:
・化石燃料消費 : 原油、石炭、天然ガスなど、エネルギー源となる資源の消費量。
・鉱物資源消費:鉄、銅、アルミニウム、レアメタルなど、製品の材料となる鉱物資源の消費量。
なぜ重要か?
これらの資源は有限です。
特に、現代の産業に不可欠なレアメタルなどは、特定の地域に偏在しているため、地政学的なリスクも抱えています。
資源の枯渇は、調達価格の高騰やサプライチェーンの寸断に直結し、企業の事業継続を脅かす重大なリスクです。
自社の製品がどの資源にどれだけ依存しているかを把握することは、将来のリスク管理の第一歩となります。
2. 水資源消費量(ウォーターフットプリント)
水は「あって当たり前」の資源ではありません。
LCAでは、「ウォーターフットプリント」という指標を用いて、製品ライフサイクル全体での水消費量と水質への影響を評価します。
これには、工場で直接使う水だけでなく、原材料の栽培(例:綿花)や部品の製造過程で間接的に使われる「見えない水(仮想水:バーチャルウォーター)」も含まれます。
なぜ重要か?
・事業継続リスク : 世界各地で水不足が深刻化しており、水は貴重な経営資源です。工場が立地する地域の水ストレス(需要逼迫度)が高い場合、取水制限などによって操業が停止するリスクがあります。
・地域社会との関係 : 水資源の過剰な利用は、地域住民の生活や農業と競合し、対立を生む可能性があります。サプライチェーン上での水リスクを把握することは、企業の社会的責任(CSR)の観点からも不可欠です。
3. 生態系への影響
私たちのビジネスは、きれいな水や空気、豊かな土壌といった、健全な生態系がもたらす「生態系サービス」の上に成り立っています。LCAでは、事業活動がこの土台に与える影響も評価します。
評価する指標の例:
・富栄養化(ふえいようか) : 工場排水や農地の肥料に含まれる窒素やリンが、川や海に流れ込み、プランクトンの異常発生(赤潮など)を引き起こして水中の生態系を破壊する影響。
・酸性化 : 化石燃料の燃焼で発生する物質が酸性雨となり、森林や湖沼にダメージを与える影響。
・生物多様性の損失 : 原材料調達のための森林伐採や土地開発が、動植物の生息地を奪い、種の絶滅を招く影響。
なぜ重要か?
生態系へのダメージは、すぐには企業の財務諸表に現れないかもしれません。
しかし、原材料を供給してくれる自然の恵みや、事業活動を支える環境そのものが損なわれれば、長期的にはビジネスの基盤そのものが揺らぎます。
生物多様性の保全は、もはや慈善活動ではなく、未来への投資なのです。
【表:CFP以外の主要なインパクト指標の例】
| 影響領域 | 評価指標の例 | なぜ重要か(ビジネスへの影響) |
|---|---|---|
| 資源消費 | 鉱物資源枯渇、化石燃料枯渇 | 原材料価格の高騰、供給不安定リスク |
| エネルギー消費 | 一次エネルギー消費量 | エネルギーコストの増大、エネルギー安全保障 |
| 水資源消費 | ウォーターフットプリント | 水不足による操業停止リスク、地域社会との対立 |
| 生態系への影響 | 富栄養化、酸性化、生物多様性損失 | 生態系サービスの劣化、ブランドイメージの低下、規制強化 |
| 人間健康への影響 | 大気汚染、有害物質排出 | 従業員や地域住民の健康被害、訴訟リスク |
まとめ:多様な影響をどう評価するか?
ここまで見てきたように、LCAはCO2だけでなく、資源枯渇、水資源消費、生態系など、非常に多くの側面から環境への影響を評価する、パワフルなツールです。
しかし、ここで新たな疑問が生まれます。
「温暖化への影響」と「水資源への影響」、あるいは「生態系への影響」。
これら性質の異なるインパクトを、私たちはどのように比較し、総合的に「どちらがより環境に良い選択か」を判断すればよいのでしょうか?
実は、これらの異なる環境影響の重要度を重み付けし、一つの指標に統合して評価しようとする考え方があります。
次回は、その代表的な評価手法である「LIME3(ライム・スリー)」について、その仕組みや考え方を詳しく解説していきます。
どうぞご期待ください。
参考文献
環境省「ウォーターフットプリント算出事例集」(平成26年8月)
https://www.env.go.jp/water/wfp/attach/jireisyu.pdf