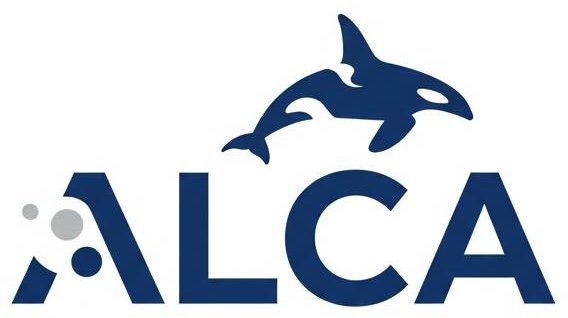はじめに
前回の記事では、LCA(ライフサイクルアセスメント)が製品のデザインや材料選定にどう貢献するかを解説しました。
しかし、製品の環境負荷は、自社の製造工程だけで決まるものではありません。
原材料の調達から部品の製造、輸送、そして最終製品が消費者の手に届くまでの「供給網全体」、すなわちサプライチェーンマネジメント(SCM)における環境負荷の可視化と改善が、今、企業にとって喫緊の課題となっています。
SCMにおけるLCAの重要性:Scope3排出量の可視化と要請の高まり
企業が排出する温室効果ガス(GHG)は、自社の直接排出(Scope1)、電力使用に伴う排出(Scope2)に加え、サプライチェーン全体から発生する間接排出(Scope3)が大きな割合を占めることが多く、その算定と削減が強く求められています。
Scope3排出量は、自社が直接管理できないサプライヤーや物流、製品の使用・廃棄など、多岐にわたる活動から発生します。
LCAは、この複雑なScope3排出量を定量的に把握し、サプライチェーン全体の環境負荷を可視化するための強力なツールとなります。
LCAを通じて、どのサプライヤー、どの工程、どの原材料が最も大きな環境負荷を生み出しているのか、その「ホットスポット」を特定できるのです。
近年、特にサプライチェーン上流に位置する企業(例:素材メーカー、部品メーカーなど)に対して、完成品メーカーやブランドオーナーといった下流の企業から、自社のScope3排出量算定のために、LCAやカーボンフットプリント(CFP)のデータ提供を求める要請が非常に強まっています。
これは、下流企業が自社のGHG排出量削減目標を達成するためには、サプライチェーン全体の排出量削減が不可欠であると認識しているためです。
この要請に応えることは、サプライヤー企業にとって、取引継続や新たなビジネスチャンス獲得のための重要な要素となっています。
LCAを用いたサプライチェーンの環境負荷可視化と改善プロセス事例
LCAをSCMに導入するプロセスは、主に以下のステップで進められます。
1. サプライチェーンのマップ化とデータ収集
まず、製品のライフサイクルに関わる全てのサプライヤーとプロセスを特定・整理します。
次に、各サプライヤーから原材料の生産量、エネルギー消費量、廃棄物量などのLCIデータを収集します。
この段階では、サプライヤーの協力が不可欠であり、データ収集の基準やフォーマットを明確にすることが重要です。
2. 環境負荷の評価とホットスポット特定
収集したLCIデータを基にLCAを実施し、各サプライチェーン段階での環境負荷(GHG排出量、水使用量など)を評価します。
これにより、環境負荷の大きい「ホットスポット」が特定されます。
3. サプライヤーとの協働による改善
ホットスポットが特定されたら、該当するサプライヤーと連携し、具体的な改善策を検討・実行します。
例えば、電子機器メーカーが部品サプライヤーと協力し、製造プロセスの省エネルギー化、再生可能エネルギーへの転換、あるいはより環境負荷の低い原材料への切り替えを行うことで、サプライチェーン全体のScope3排出量を削減します。
透明性向上とトレーサビリティの重要性
サプライチェーンの環境負荷を正確に把握し、改善を進めるためには、透明性の確保が不可欠です。
特に、原材料の調達から最終製品に至るまでの経路や環境情報を追跡できる「トレーサビリティ」の確保が重要になります。
トレーサビリティのメリット
| 正確なデータ収集 | どこで、どのような環境負荷が発生しているかを正確に把握できます。 |
|---|---|
| リスク管理 | 環境・社会的なリスクが高いサプライヤーや工程を特定し、事前に対策を講じることができます。 |
| 信頼性向上 | 消費者や投資家に対し、製品の環境配慮に関する信頼性の高い情報を提供できます。 |
透明性向上の手法
| サプライヤーエンゲージメント | サプライヤーに対し、環境データ開示の要請や、LCAに関するトレーニングを提供し、協力を促します。 |
|---|---|
| デジタル技術の活用 | ブロックチェーン技術などを活用し、サプライチェーン上の環境データをセキュアに共有・管理することで、トレーサビリティと透明性を飛躍的に向上させる取り組みも始まっています。 |
まとめ
LCAは、SCMにおいてScope3排出量を可視化し、サプライチェーン全体の環境負荷を削減するための不可欠なツールです。
サプライヤーとの連携、そしてトレーサビリティの確保による透明性向上は、持続可能なサプライチェーンを構築する上で極めて重要です。
特に、上流企業へのLCA/CFPデータ提供要請の高まりは、この取り組みの喫緊性を物語っています。
次回は、LCAの結果がどのようにエコラベルの取得や統合報告書といった外部への情報開示に活用され、企業の環境コミュニケーションを強化していくのかについて解説します。